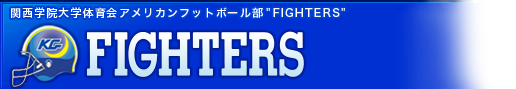- トップ
- 部紹介
- 歴史・戦績
- 米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
- 米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
- 第9章 Tフォーメイションの拡大
米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
第9章 Tフォーメイションの拡大
1959/02/28
1912年に最後の基礎的なルールの修正があって以後、アメリカン・フットボール界に起こった変革の中では、1940年に紹介された新しいTフォーメイションの復活ほど影響力の大きいものはない。これはルールの変更にはなんら関係ない戦術面の一大改革であり、このとき以後T全盛の現在の姿を生み出す推進力となったものである。
アメリカン・フットボールの初期の姿は現在のTと似通ったものであり、これをオールドTとして区別している。1888年にオールドTが初めて出現してから、マス・プレーの混乱期を経てフォワード・パスの採用、ウィングバック、シフトの発展とフットボールの歩みがつづけられたが、この間、Tフォーメイションは攻撃の基本型として依然その姿を保っていた。ノートルダム大学がその全盛期にTからボックスへシフトしてその効果をあげ、ときにはシフトせずにTプレーそのものを使うようなこともあったが、1924年、1927年、1930年のシフトに関するルールの変更により、一時期を画したノートルダム・ボックスも下火となった。その結果、ダブル・ウィングを初めとする典型的なウィング・バックの流行とともに、さらに何か新しいものを求めようとする機運が、ついにモダーンTを導き出したということができる。その開花は1940年のスタンフォード大学、およびプロ・フットボールのシカゴ・ベアズ(Chicago Bears)における大成功であった。
1 オールドTの時代
オールドTは1888年のルール変更の結果として生まれた。それまでラインは両腕を広くひろげて立ち、HBは7~8ヤード、FBは10~11ヤードも深い位置でプレーしていたが、この年、ロー・タックルの規定とブロッキングを合法とする改革案が示されたため、ライン、バックともに現在のフォーメイションにかなり近いほど接近して動くようになり、オールドTが一般的なものとして使われ始めた。
最初QBはセンターから約10センチ離れ、センターから送られるボールのリバウンドを取るために片膝をついて低く構えていたが、1894年シカゴ大学のコーチ、スタッグはファンブルを避けるためQBに腰高の姿勢で直接センターからのボールを取らせ、現在のQBの位置を初めて生み出した。
初期のオールドTはラインが肩と肩を並べる、いわゆるタイトTの形であり、その狙いはタックルの位置に力を結集することであった。そしてもっぱら力に頼り、スピードとトリックにはまだ強調点を置いていなかった。
この単純なオールドTに種々の変化を持ち込んだ第一人者は、またもシカゴ大学のスタッグであり、モダーンTの必須部分を早くも創案している。まず1898年には現在のマン・イン・モーション(man in motion)と同じ原理のフライア(flier)と名付ける変化を考案し、引きつづきディレイド・バック(delayed buck)、キープ・プレー(keep play)、フランカー(flanker)、フェイク・パス(fake pass)、オプション・プレー(option play)、ペディンガー(pedinger)などの変化を実戦に採用している。
2 ベアズTの展開
1920年に新しくできたプロのナショナル・リーグにシカゴ・ベアズ(Chicago Bears)が加盟し、変化に富む種々のフォーメイションを用いたが、その一つにTも含まれていた。その後1930年にコーチとなったジョーンズ(R. Jones)が当時の最大のスター、グレンジ(Red Grange)を使ってマン・イン・モーションを効果的に用い、ラトラル・プレーやパス・プレーに成功をみせた。このため相手チームは守備陣を拡げねばならず、ベアズはパスの威力とともに相手の拡がったラインを衝くラン・プレーに成功をみせるようになった。
1933年からはジョーンズに代わってオーナーのハラス(G. Halas)が実戦の指揮を取り始め、種々の新機軸を加えていったが、1937年にはシカゴ大学のショーネス(C. Shaghness)コーチがベアズの顧問として参加し、ベアズTの向上に力を尽くした。この間、ベアズの好敵手たるグリーンベイ・パッカーズ(Green Bay Packers)、デトロイト・ライオンズ(Detroit Lions)などが回転式5-4-2守備法(revolving5-4-2defense)を考え出してベアズのラン、パスの機動性を封じようとしたが、これに対しベアズはまたも1939年にカウンター・プレー(counter play)をうまく使って5-4-2に対抗した。こうして1940年の画期的なベアズの全盛期が到来するが、その攻法はいわゆるワイド・オープンTの端緒であった。
この新戦法は名QBのラックマン(Sid Luckman)を擁して最大の効果をあげ、ワシントン・レッドスキンズ(Washington Redskins)を73-0で大破してその年の覇権を獲得した。このベアズTの新戦法はそれまでの重々しい型のTから一転して、スピードとタイミングに主眼を置くモダーンT時代への契機となった。
ベアズTの特徴をあげると、
(1) ベアズの作り出したワイド・オープンTはエンドを広くひろげるとともに、左右どちらかにマン・イン・モーションを送り、フィールド一ぱいを使って攻撃地域を著しく拡大した。
(2) シグナル・システムの使用により、エンドとバックの変化をつけるとともに、ラインも適宜シフトを変え、まず相手の守備型に混乱を起こさせた。
(3) 数種のフランカーやマン・イン・モーションの使用によってベアズTは実質的にはノートルダム式のボックスやワーナー流のダブルウィングに似た攻撃型に移行するわけであり、単にTというにとどまらず、あらゆる攻撃型を綜合した幅広い力を持ち、機に応じて適宜フォーメイションを使い分けながらTDを狙うという行き方であった。
3 スタンフォードTの成功
シカゴ大学のコーチをしながらベアズTの計画にも参加していたショーネスは1939年、スタンフォード大学に移り、翌1940年にはベアズTを取り入れて猛威をふるい、大学フットボール史上でも特筆されるほどの強いチームを作り出した。その4人のバックフィールドはアルバート(F. Albert)を初め、すばらしい名手をそろえてシンデレラ・ボーイズ(Cinderella boys)と呼ばれた。この年、スタンフォード大学はリーグでは10戦全勝で優勝、ローズ・ボウルにも出場してネブラスカ大学を一蹴した。
4 モダーンTの性格
シカゴ・ベアズとスタンフォード大学の成功から、またたく間に全国を風靡したモダーンTは、何よりもスピードとタイミングに主眼を置いた。従来のようにパワーに頼り、緩慢な型のフットボールはすでに過去のものとなり、全体のスピードと機械的なタイミングが大いに強調された。攻撃力のカギといわれるブロッキングも、力の限りをつくして相手を押し倒す必要はなく、単に最も妥当な時間に相手の動きを一瞬止めるだけで十分であった。その瞬間にボール保持者がサッと走り抜けるという具合に綿密に組み立てられ、チームの全員が一糸乱れず忠実な動きをすることが何よりも求められた。この結果、個人的な力、技術といったものよりも、各人がまったく分業的にそれぞれの機能を果たしながら、しかも全体のバランスを問題にするという機能的フットボール、科学としてのフットボールへの道に大きく踏み入れることになった。
5 スプリットT(split T)の出現
ベアズTが猛威をふるったわずか1年後の1941年に、早くもTの変型たるスプリットTがミズーリ大学のファーロー(Don Faurot)によって発明された。ファーローは1939年に名パサー、クリスマン(Paul Christman)を使ってシングル・ウィングで覇権を得たが、クリスマンの卒業とともに攻撃法の転換を考え始め、スプリットTの実験に取りかかった。ファーローがスプリットTを選んだのは、
(1) 卓越した名手がいなくても平均した選手がいさえすればよい
(2) 1プレー当たりの平均獲得距離が多くなる。ためにロング・ランはなくとも着実なペースを保つことができる。
(3) バックスはより多くオープンに出ていくことができる
(4) 標準的な守備法に大きな圧力を加えることができるなどの理由からであった。
スプリットTの特徴としては、第一にラインの広い間隔、第二にQBのスライド、第三にボール保持者たる新しいQBの機能、第四に複雑なトリックなどが挙げられる。
ラインの間隔を最初から広く開いているのは“バックスの通るべき穴はすでに存在する”という考え方であり、従来のタイトTにおいてラインが力をつくして相手を押しのけてバックスの進路を作っていたことに比べると、すばらしい着想というべきものであった。したがってスプリットTのラインズは穴を作る労力から、すでに存在する穴を維持するだけに腐心すればよかった。またQBは単にボールの仲介者たる域を脱し、スピンを捨てて横にスライドし、自らボールを持ったまま走るキープ・プレーをカギとして、しばしばオープン攻撃に威力を加えることができた。
1941年のミズーリ大学はこのすばらしいスタイルに道を開き、1ゲーム当たりランによる平均獲得距離において全米一の好記録を作った。そして彼の教えを受けたウィルキンソン(Bud Wilkinson)はオクラホマ大学において、またテイタム(Jim Tatum)はメリーランド大学において強力きわまりないスプリットTチームを生み出し、1954年のアーミー対ネービー戦で、ネービーが見せたスプリットTもそのプレーの可能性を明瞭に示した実例であった。
6 ウィングT(wing T)
1940年代に流行したもう一つのTの変型ウィングTである。そのアイディアはTとシングル・ウィングの一番いい内容を取って一つのフォーメイションに結びつけることであり、コロンビア大学のリトル(Lou Little)がその第一人者として知られる。彼は1944年の後半からウィングTを取り上げ、とくにすぐれたパス・プレーに妙味をみせた。
7 Tダブル・ウィング(T double wing)
もう一つの注目すべきTの変形が1950年代に姿を見せ、Tダブル・ウィングといわれた。これはミシガン州立大学のマン(Clarence Munn)が開拓し、1953年に最もすばらしいチームを作り出した。そのアイディアはその名の示すごとく、Tとダブル・ウィングを結びつけたものであり、この新戦法を使ってミシガン州立大学は1950年から3年間に、わずか1敗という快記録を残した。