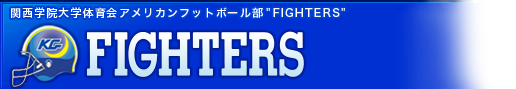米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
第4章 アメリカン・フットボールへの移行
1959/02/28
大学フットボール協会は設立の年から年々一回乃至それ以上の会議を開いていたが、この会議はすべて学生の代表によって組織され、参加選手の資格を問題とするよりもルールの協定を取扱っていた。1881年に前年度のエール大学の卒業生であるキャンプ(Walter Camp)がこの会議に出席するようになり、以後は卒業生も会議の要員としてフットボールの発展に力を籍した。”アメリカン・フットボールの父”といわれるキャンプはこの会議を年々主宰し、アメリカン・フットボールを独自の域に引き上げるための数々の重要なルール制定を指導した。その中にはスクリメージの採用、ダウンと獲得ヤードの制度確立、合理的な得点数の決定などが含まれている。他面競技が次第に拡大するとともに恐ろしいマス・プレー(mass play)が姿を現わし始め、ゲームは粗暴極まりないものとなって数々の問題を提供した。ために1885年、ハーバード大学がフットボールを二年間禁止するなど、多少学校当局の関心が見られるようになった。
1 スクリメージの採用と11人案の実現
1880年に極めて影響力の大きい変更が行われた。その一つはエール大学が長い間主張しつづけていた一チーム11人案の実現であり、いま一つはラグビー式スクラムを廃し、近代スクリメージを採用することによってボール保持の原則を確立したことである。
従来のラグビー・スクラムではボールの所有がどちらのチームにあるのか判然とせず、従ってボールをプレーに移し、つづいて起こる戦略を意識的・能動的に準備する権利もなかった。これに対しキャンプの作ったスクリメージ案は、ボールをつねに一方のセンターの所有下におき、センターだけがスナップ・バックでボールをプレーに移すことができた。そしてセンターからのスナップを最初に受け取るQBがここに出現し、ボールを自由にコントロールできる攻撃チームは進んでプレーを組み立てることができ、QBのシグナルの使用によってよりよきチーム・プレーを可能ならしめた。
選手の数を15人から11人に減らすさい、この11人の配置の方法が大きな課題となった。そしてハーバード大学のライン7名、HB3名、FB1名とし、HBのうち1人が交互にQBとなる案、プリンストン大学のライン6名、QB1名、HB2名、FB2名という案などが提示されたが、エール大学はライン7名、QB1名、HB2名、FB1名という配置案を出し、これが徐々に支配的なものとなっていった。
また1870年代の終りごろ、ラインの各位置の名称をどうするかという問題が起こった。ラインの一番端の位置は最初から英国のラグビー式にエンド・ラッシュ(end rush)と呼ばれたが、その隣りはネックスト・ツ・エンド(next to end)、三番目はネックスト・ツ・センター(next to center)、中央の者は勿論センターと命名された。しかしネックスト・ツ・エンドの位置にある者が、ラインの中で他の誰よりも多くタックルをするということが判ると、その選手はタックラーとして名を知られるようになり、やがてその名称もタックル(Tackle)と変わった。同じようにセンターが足でボールをスナップ・バックする時に、ネックスト・ツ・センターがセンターを支えて護衛していることに気がつき、それ以後その位置の名称もガード(Guard)と呼ばれるようになった。
他の変更としてはフィールドの大きさが140ヤード~70ヤードから110ヤード~53ヤードとなり、ゴールから25ヤードの地点に十字の印がつけられ、キック・オフはフィールドの中央から行われるようになった。
2 ダウンの制度確立
1882年になるとダウンの方法が確立して、さらに大きな進歩をとげたが、これが近代フットボールの端緒であるといってよい。1880年に作られたスクリメージによるボール保持の原則は攻撃チームの戦術面に大きな力を与えたが、ボールの保持チームには何らダウン数の制限もなく、また獲得すべきヤード数に関する規定もなくて、ただパントか、フィールド・ゴールの使用によってボールを交換したものであった。
当時の習慣として試合がタイの場合には、前年の勝者にそのまま勝利を授けるということになっていたが、その場合のタイはそのまま勝利を意味するものであった。1880年のエール・プリンストン戦で、プリンストン大学のロニー主将は敢て試合を引分に終らせるためボールを蹴らずに、ただ莫然とボールを持ちつづけようとし、翌1881年にもトスに勝ったプリンストン大学は前年同様に、ボールを一度も蹴らずにずっとスクリメージをつづけ、得点はなかったが、前半ずっとボールを放さなかった。これに対抗したエール大学も後半ずっとボールを保持しつづけ、互いに無得点のまま試合を終った。この極端な封鎖戦術は聴衆に嫌がられて次第に非難の的となり、これにあきたらずとする気持ちからダウンの設立が導かれた。
やがて1882年の大学会議において「ダウンと獲得すべきヤード数」の有名なルールが採用され、改革の手が打たれた。このルールは「3回の連続的な攻撃ダウンのうちに5ヤード前進していないか、または10ヤード後退していない場合は最後のダウンの地点で相手にボールを渡す」というものであり、この革命的なルールに従ってボールは互いに交換され、攻守を力に応じて分担するようになった。これ以来フィールドには5ヤードごとの白い線がつけられ、グリディロン(gridiron)という名が一般的なものとなっていった。 5ヤード・ルールの設定はゲームの戦術研究、ひいてはフットボールの発達を大いに助長させたが、この制限距離獲得の手段としてこの時代から、従来の軽量敏捷な選手に代って強力な巨人を選ぶようになってきた。1882年のエール大学は、当時としては想像もつかぬ重量チームとして姿を現わし、短い強力なラッシュによるプレーを発達させた。このシステムが大いに功を奏したので、翌年はほとんどの学校がこれにならい、こうしてモダーン・ランニング・アタックの先鞭をつけるとともに、やがて問題化した猛烈なマス・プレーの発端ともなった。
3 得点数の決定
1883年にいま一つの重要な変更が行なわれたが、これを紹介したのもキャンプであった。それはゴール、タッチダウン、セフティに関する得点数の問題であった。これは前年のハーバード・プリンストン戦で、両校が互いに勝者であるといって激しい論争を巻き起こした事件に由来する。
その試合はハーバード大学がまずタッチダウンを記録し、トライをミスしたが、そのあとでゴール・フロム・フィールドを成功させた。一方プリンストン大学はタッチダウンをし、引きつづき名手ハクザールがゴール・オン・ザ・トライ(goal on the try)を成功した。そこで両チームは互いに自分の方のゴールが優れていると主張してともに勝利を叫んだ。レフェリーをしていたエール大学のワトソンはハーバード大学の勝を認めたが、プリンストン大学はこの判定を不服とし、数年間は自ら勝者だといいつづけた。
当時の得点法は数字的なシステムではなく、プレーとプレーのバランスを考えて作られたものであった。そのためゴール・フロム・フィールドはタッチ・ダウンよりも上位だが、4TDはゴール・フロム・フィールドより優先するという具合であり、勝ち敗けがセフティに関する時には4セフティ少ない方をもって勝とした。このシステムは実際面から見て完全なものでなく、納得しかねる面を多分に持っていたため、勝敗をめぐってしばしば喧嘩口論のタネとなった。そこでキャンプは1883年10月17日の会議で明確な得点方式を紹介し、得点となるプレーに対して与えられる基本的な評価はセフティ1点、タッチ・ダウン2点、ゴール・フロム・ア・トライ4点、ゴール・フロム・フィールド5点とした。1884年にはこの得点法はまた変更され、タッチ・ダウン4点、ゴール・アフタ・タッチ・ダウン2点、セフティ2点となった。
同じ1883年、これまで両チームから出ていたジャッジが廃止され、レフェリーがただ一人でゲームを運営するようになった。それまでのジャッジは互いに自チームを積極的に弁護する義務を担い、ゲームに対する知識よりも議論をする能力によって選ばれたというほど徹底したものであったため、レフェリーはプレーの運行を司るとともに、両ジャッジの意見の不統一を調整するのに大いに悩まされたものであった。
4 Vトリック及び援護走者の出現
アメリカン・フットボールの持つ特徴の中で、援護走者(interference)やブロッキング(blocking)ほど判然としたものはない。1884年にプリンストン及びリハイ(Lehigh)の両校でVトリックなるマス・プレーが初めて使用され、また援護走者がアメリカン・フットボールの一局面となって姿を現わした。
Vトリックまたはウェッジ(wedge)と呼ばれるマス・プレーはプリンストン大学のQBホッジが創始し、同じころリハイ大学のロブソンもこれらを工夫したといわれる。プリンストン大学はこのプレーを対ペンシルヴァニア戦の後半で使った。Vトリックというのは7人のラインをがっちりしたV型の集団とし、ランナーを内側に入れた逆V字の形を取って、集団の威力でランナーを護り、大きな前進を企図したものである。このプレーは物凄い威力をみせて一躍タッチ・ダウンを取ったが、しかしその時は一時的なシフトに過ぎないと考えられ、大した考慮も払われなかった。その後プリンストン大学は4年後の対エール戦後半のオープニング・プレーとして、再びVトリックを使用した。この機械的なV型攻撃は以後今日のキック・オフと同様、オープニング・プレーの決まった形としてさらに4年間つづけられた。
援護走者を始めて使用したのもプリンストン大学であり、最初はガーディング(guarding)という名で呼ばれていた。1879年プリンストン大学は対ハーバード戦で、ボール保持者を護るために二人の選手を左右の真横においた。レフェリーをしていたキャンプ(W. Camp)はこれを反則だと警告したが、彼にも明確な宣告を下す自信はなかったようであり、そのシーズン末期にはエール大学でも同じプレーを使った。
このブロック戦術は大方のチームの賛意を受けたが、1884年プリンストン大学は思い切ってボール保持者の前に援護走者をおいた。そしてこれにならった他の大学でも同じ形を取って対抗するようになり、ラグビー式のオフサイド・ルールは事実上ここに撤廃されることになった(ルールで実際に廃止されたのは1906年である)。それまでボール保持者は、専ら個人技だけを頼りに勝手にプレーしていたものだが、援護走者の出現があってから、これを利用して全体の中でプレーするようになり、援護走者が攻撃の要諦として次第に重要なウエイトを占めていくようになった。
5 激しい競技内容と教授会の態度
当時のゲーム内容について、ハイズマンがスポーツ百科事典(The Encyclopedia of Sports)に詳述している。--当時の選手は週に二回、水曜と土曜にゲームをしていたから、文字通り鉄の如き頑丈な身体でなければならなかった。一度ゲームが始まると実際に負傷するか、また少なくともケガだという口実でもなければ試合場を離れることは出来なかった。従って主将が誰かを交代させようと思えば「腕をへし折るなりどうなりしろ」と小声でいったものである。危険防止のため今日使用しているヘルメットとかパッドの類はまだ姿を見せず、たまたま自家製のパッドを使用しようものなら、卑怯者呼ばわりされたものである。頭を保護するものは髪の毛だけで、選手は6月の始めから髪を長く伸ばして準備をした。神学生と医学生は顎髭をのばすことも許されていたので、彼らの容貌はゴリラのそれの如くであったといわれる。ジャージ、ショート・パンツなどが普く用いられるようになり、ジャージの上にキャンパス付のジャケツを着ていた。ラインメンは攻守ともまっすぐに突っ立って相対し、互いに狂ったごとくなぐり合いを演じて相手を倒そうとしたものであり、それに対 する罰則は全然なかった。従って当時のラインメンは文字通り物凄いボクサーであり、スラッガーでなければならなかったわけである。タックルは腰及び腰の上に制限するというルールはあったが、技術的な研究は全然なされずただ実戦に臨んでがむしゃらに首を持ってねじり倒すといった類のものであった。
こうしてフットボールは若人の激情をそのまま発揮する肉体の闘争となり、ややもすれば学生スポーツとしての正しい発達が阻害される有様であった。1885年ハーバード大学の教授会は競技委員会の勧告により、プレーが乱暴であるとの理由でフットボールを2年間禁止した。その他の大学でもフットボールの統制に関して多少関心は持たれてはいたが、学校当局の態度は概ねスポーツに対して黙認または放任主義的であったように思われる。
6 各地への拡大
初期のフットボール界をリードしたエール、プリンストン、ハーバード、コロンビアなどの諸大学のほか、1870年代末にはフットボールは数々の大学に拡大していった。スチーブンス、タフツ、ニューヨーク市立大学、ブラウン、アマースト、ダートマスなど、北東部の大学がまずフットボールを取り上げたほか、南部ではワシントン・アンド・リー大学とヴァージニア陸軍大学が1877年に初めてゲームをやった。中西部では1878年にミシガン大学とラシーン大学が初めてチームを作り、ミシガン大学は1881年チームを東部に送ってハーバード、プリンストン、エールの諸大学とプレーした。こうしてフットボールの大衆的な人気はますます増大して行き、さらに西部のコーネル、フォーダム、ミネソタ、パーデュー、ノートルダム、インディアナ、サザーン・カリフォルニア、カリフォルニアなど、後年の強力チームもこのころに初めてチームを作り上げた。
アーカイブ
- 2025年1月(5)
- 2024年12月(3)
- 2024年11月(13)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(6)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(9)
- 2024年5月(11)
- 2024年4月(6)
- 2024年3月(7)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(4)
- 2023年12月(10)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(1)
- 2023年6月(6)
- 2023年5月(6)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(4)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(6)
- 2022年12月(10)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(4)
- 2022年9月(4)
- 2022年8月(3)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(4)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(6)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(9)
- 2021年11月(5)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(4)
- 2021年8月(1)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(7)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(3)
- 2021年2月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(2)
- 2020年9月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年4月(7)
- 2020年3月(2)
- 2020年2月(9)
- 2020年1月(8)
- 2019年12月(12)
- 2019年11月(7)
- 2019年10月(4)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(2)
- 2019年7月(1)
- 2019年6月(5)
- 2019年5月(8)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(8)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(4)
- 2018年12月(11)
- 2018年11月(6)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(4)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(5)
- 2018年5月(5)
- 2018年4月(6)
- 2018年3月(9)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(5)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(6)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(6)
- 2017年2月(4)
- 2017年1月(5)
- 2016年12月(11)
- 2016年11月(7)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(4)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年6月(11)
- 2016年5月(6)
- 2016年4月(4)
- 2016年3月(9)
- 2016年2月(4)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(9)
- 2015年10月(2)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(3)
- 2015年7月(3)
- 2015年6月(7)
- 2015年5月(3)
- 2015年4月(2)
- 2015年3月(8)
- 2015年2月(6)
- 2015年1月(3)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(7)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(3)
- 2014年8月(4)
- 2014年7月(8)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(10)
- 2014年4月(4)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(6)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(10)
- 2013年11月(7)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(3)
- 2013年7月(5)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(5)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(5)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(8)
- 2012年11月(7)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(3)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(7)
- 2012年5月(4)
- 2012年4月(5)
- 2012年3月(6)
- 2012年2月(6)
- 2012年1月(2)
- 2011年12月(8)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(4)
- 2011年9月(4)
- 2011年8月(3)
- 2011年7月(3)
- 2011年6月(6)
- 2011年5月(6)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(9)
- 2011年2月(4)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(6)
- 2010年11月(14)
- 2010年10月(4)
- 2010年9月(3)
- 2010年8月(3)
- 2010年7月(3)
- 2010年6月(6)
- 2010年5月(4)
- 2010年4月(9)
- 2010年3月(7)
- 2010年2月(7)
- 2009年12月(1)
- 2009年11月(2)
- 2009年10月(2)
- 2009年9月(2)
- 2009年8月(4)
- 2009年7月(5)
- 2009年6月(8)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(7)
- 2009年3月(10)
- 2009年2月(3)
- 2009年1月(1)
- 2008年12月(1)
- 2008年11月(4)
- 2008年10月(2)
- 2008年9月(3)
- 2008年8月(2)
- 2008年7月(1)
- 2008年6月(5)
- 2008年5月(2)
- 2008年4月(4)
- 2008年3月(6)
- 2008年2月(1)
- 2008年1月(6)
- 2007年12月(2)
- 2007年11月(2)
- 2007年10月(2)
- 2007年9月(3)
- 2007年8月(4)
- 2007年7月(5)
- 2007年6月(8)
- 2007年5月(5)
- 2007年4月(9)
- 2007年3月(11)
- 2007年2月(3)
- 2007年1月(6)
- 2006年12月(3)
- 2006年11月(3)
- 2006年10月(4)
- 2006年9月(2)
- 2006年8月(7)
- 2006年7月(3)
- 2006年6月(7)
- 2006年5月(6)
- 2006年4月(6)
- 2006年3月(6)
- 2006年2月(3)
- 2006年1月(3)
- 2005年12月(1)
- 2005年11月(2)
- 2005年10月(3)
- 2005年9月(2)
- 2005年8月(8)
- 2005年7月(1)
- 2005年6月(4)
- 2005年5月(6)
- 2005年4月(6)
- 2005年3月(6)
- 2005年2月(4)
- 2005年1月(3)
- 2004年12月(1)
- 2004年11月(2)
- 2004年10月(3)
- 2004年9月(3)
- 2004年8月(2)
- 2004年7月(2)
- 2004年6月(3)
- 2004年5月(3)
- 2004年4月(4)
- 2004年3月(10)
- 2004年2月(1)
- 2004年1月(4)
- 2003年11月(3)
- 2003年10月(2)
- 2003年9月(3)
- 2003年8月(16)
- 2003年7月(1)
- 2003年6月(5)
- 2003年5月(3)
- 2003年4月(4)
- 2003年3月(8)
- 2003年2月(4)
- 2003年1月(3)
- 2002年11月(3)
- 2002年10月(2)
- 2002年9月(3)
- 2002年8月(2)
- 2002年7月(3)
- 2002年6月(5)
- 2002年5月(5)
- 2002年4月(4)
- 2002年3月(6)
- 2002年2月(6)
- 2002年1月(6)
- 2001年12月(4)
- 2001年11月(2)
- 2001年10月(4)
- 2001年9月(3)
- 2001年8月(2)
- 2001年7月(5)
- 2001年6月(5)
- 2001年5月(3)
- 2001年4月(4)
- 2001年3月(14)
- 2001年2月(3)
- 2001年1月(2)
- 2000年12月(2)
- 2000年11月(2)
- 2000年10月(4)
- 2000年9月(3)
- 2000年8月(3)
- 2000年7月(6)
- 2000年6月(3)
- 2000年5月(3)
- 2000年4月(3)
- 2000年3月(5)
- 2000年2月(4)
- 2000年1月(5)
- 1999年12月(4)
- 1999年11月(3)
- 1999年10月(2)
- 1999年9月(3)
- 1999年8月(1)
- 1999年7月(3)
- 1999年6月(3)
- 1999年5月(6)
- 1999年4月(4)
- 1999年3月(5)
- 1999年1月(3)
- 1997年12月(3)
- 1997年11月(2)
- 1997年10月(2)
- 1997年9月(3)
- 1997年8月(1)
- 1997年7月(2)
- 1997年6月(8)
- 1997年5月(5)
- 1997年4月(4)
- 1997年3月(4)
- 1997年2月(1)
- 1997年1月(3)
- 1991年2月(6)
- 1959年2月(11)