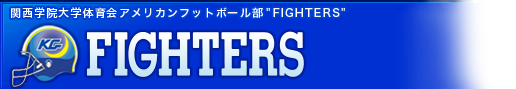米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
第6章 フォワード・パス時代始まる
1959/02/28
1906年1月12日の会議によってフォワード・パスが公認された。これはスクリメージとダウンの制度がアメリカン・フットボールに確固たる形態を与えて以来、最大の影響力を及ぼしたものであった。このため、力のみに頼るマス・プレーに代って有機的スポーツとしてのフットボール時代が始まり、選手、観客、いずれにも多大の魅力を与えた。しかしルール制定によって一躍フォワード・パス時代が現出したわけではなく、なお暫くは旧態依然たる数年がつづいた。1913年、ウエスト・ポイントに於ける対アーミー戦でノートルダム大学が演じたすばらしいフォーワード・パスの妙味は全国的な反響を呼び、ここに漸くフォワード・パスへの実質的な眼が開かれるに至った。その意味でこのゲームの価値は1875年のハーバード・マックギル戦に匹敵するものであり、1913年をもって近代フットボールは始まるといってよい。
1 改革案の根本精神
フォワード・パスの公認がアメリカン・フットボールに強烈な影響を及ぼしたのはその後の歴史の流れによって導かれたものであり、1906年の会議に於ては数多くのルール変更のうちのほんの一項目というに止まった。そして変更の大部分のものはプレーの荒っぽさを少なくして選手の危険をなくし、同時にゲームを観衆にとってもっと親しみ易いものにするという意図でなされた。ルール委員会がルール変更に当って取った根本的な態度は
(1) 選手にとってゲームより安全、かつ興味あるものとすること
(2) ゲームを明らかによりオープンなものとすること
(3) 体重によってゲームが左右される傾向を排し、スピードと敏捷性と頭脳的プレーにより大きな機会を与えること
(4) より広範な戦術的可能性を提供し、軽量のチーム、小さな大学のチームにも真の機会を与えること
(5) 審判技術の発達をうながし、ゲームに関するスポーツマンシップの標準を高くし、ルールを乱そうとする絶えざる誘惑をなくすこと
などであった。
2 フォワード・パスのアイディア
フォワード・パスが合法となったのは1906年だが、それ以前にゲーム中にフォワード・パスが使用された例として二つの場合が挙げられる。その第一は1876年のエール・プリンストン戦でエール大学のキャンプがタックルされた時に前方にいたトムプソン(O. Thompson)にボールを投げ、そのままトムプソンが走りつづけてTDを記録したといわれる。プリンストン大学はこれに抗議し、反則だとつめよったが、審判はその決定のためにコインを投げTDを許すことに決めた。第二の例はノースカロライナ大学とジョージア大学の試合でみられた。この試合でノースカロライナ大学のフルバックが前方にいたチームの者にボールを投げ、それが70ヤードに及ぶロング・ランとなってTDを記録した。ジョージアのコーチをしていたワーナー(G. Warner)が当然の如く反則だと抗議したが、審判はそのプレーを見ていなかったといってTDを認めた。たまたまこのゲームを見ていたハイズマンはこの規則違反のプレーこそゲームをオープンに展開し、プレーの荒っぽさをなくするために是非とも必要なたものだと判断し、数年後、彼によってフ ォワード・パス合法化のアイディアがルール委員会に提案された。 ハイズマンとともにネービーのダッシェル(P. Dashiell)大尉、ペンシルヴァニア大学のベル(John C. Bell)ミネソタ大学のウィリアム博士、セントルイス大学のコクム(E. Cochems)らもフォワード・パスを最初に提唱した人々であり、その発展に重要な役割を演じた。しかし彼らの意図は抑圧されたマス・プレーを和らげるための一手段としてのフォワード・パスを考えたに止まり、その出現がフットボール界に革命を導くことを予見することはできなかった。
3 フォワード・パスの使用と初期の認識
合法的となったフォワード・パスを初めてゲームに持ちこんだものについては二、三の説がある。しかし権威筋から最も妥当と認められているのはセントルイス大学のコーチ・コクムである。
彼は1906年6月、チームをシカゴ北方のベンラ(Benlah)湖畔に連れていってパスの研究の緒についた。彼は楕円のボールの形から長軸に沿った7本の紐の部分を観察した結果、ボールの先端に一番近い2本の紐の間に指を置き、長軸に沿って手首をねじるようにして投げる方法を発見した。このやり方でロビンソン(Bred Robenon)をパーサーに仕込み、今日の方法と大差ない投げ方でロング・パスを投げる技術を教えた。ロビンソンはボールを強く、しかもレシーバーに正確に投げ、現在のパス攻撃スタイルの先鞭をつけた。彼がゲームで初めてフォワード・パスを投げたのは1906年9月の対キャロル(Carroll)戦であった。彼はオーバーハンドから長短自在の効果的なパスを投げて大きな大学をつぎつぎと破り、1906年の成績は全勝、総得点402点、失点わずか11という抜群のものであった。ロビンソンの投げたパスの資料として1906年11月3日の対カンサス戦で彼からシュナイダー(J. Schneider)に渡ったものの図解があり、それには”そのシーズン最長のパス…48ヤード”と見出しがついている。
1906年10月3日、コネチカット州のウェスレイヤン(Wesleyan)大学が対エール戦でオーバーハンドのフォワード・パスを初めて完成させたという説がある。このパスはモーア(Sammy Moore)からタッセル(I. Van Tassell)に投げ、18ヤードを得たといわれる。ウェスレイヤンのコーチ、ライター(H. R. Reiter)は1903年に、もとのカーリッスル・インディアン(Carlisle Indian)の選手からボールを回転させながら投げる方法を習い、フォワード・パスが合法となった年に早速これを使用したものだという。
また一説としてエール大学の名選手、キルパトリック(John Reed Kilpatrick)がオーバーハンドでフォワード・パスを初めて投げたのは自分だと主張している。1907年秋の対プリンストン戦で、キックとみせてフォワード・パスを投げ、それでTDを記録したというが、時期的にはやはりその前年のセントルイス大学が先行するようである。
東部の一流大学の中でフォワード・パスを最初に使用したのは1906年のエール大学である。彼らはその年のハーバード戦で、どんな攻撃を仕向けても失敗ばかりしていたのでとうとう、フォワード・パス使用を思いつき、ヴィーダー(P. L. Veeder)がフォーブス(R. W. Forbes)に30ヤードのパスを投げて一躍ゴール寸前にまで進み、つづくプレーでTDを挙げることができ、6~0でハーバード大学を降した。
ルールに取り上げられたフォワード・パスを各地のコーチ連が見逃すはずはなく、以上の諸校に見られたようにどのコーチも一様にフォワード・パスを使用しようとした事実はある。しかしその何れもが、フォワード・パスをもって攻撃の主武器とする決断はみせず、原則的にはパスの使用をほのめかすことによって守備側のバックフィールドを広く散開せしめ、攻撃を有利に展開することを図ったものであった。そうしたフォワード・パス軽視の観念は特に一流大学に強く逆に新興地域とみなされる中西部ではその点に於て東部に一歩先んじるものあった。シカゴ大学のコーチ・スタッグは早くも1906年には64のフォワード・パス攻撃型を作って効果をあげ、1907年、1908年には覇権を握っているが、そのアイディアは今日考えられるフォワード・パスのすべてを網羅しているといってよい。1907年にはミシガン大学のヨスト(F. Yost)カーリッスル大学のワーナー(Pop Warner)らも優秀なパスの威力を示した。
4 改革案つづく……1906年
1906年の会議でフォワード・パス合法化のほかに効果のあった変更は
(1) ゲームの時間を70分から60分と短縮し、前後半30分に分けた
(2) スクリメージのさい、攻防両チームの間に中立地帯(neutral zone)を設定してボールの幅だけ両チームを離れさせた
(3) 3ダウンのうちに前進すべき距離を5ヤードから10ヤードとした
(4) ラインマンがバックフィールドに下る時にはスクリメージより5ヤード以上後退しなければならない
(5) ハードリング(hurdling)の禁止
などであるが、これらは何れもゲームの安全化を図って打ち出された改革である。このうち中立地帯の設定はゲームの粗暴性を除き、プレーの円滑を図るための最大の要素であった。それ以前のフットボールといえば両軍のラインメンがボールの中心線を通る仮想のスクリメージ・ライン上にひしめき合い、互にヒタイとヒタイ、足と足をくっつけて立ち、激しく口論し合い、猛烈にぶつかり合ってゲームの激化に拍車を掛けていた。この中立地帯の設定以来、攻撃側、守備側の両スクリメージ・ラインが確定し、”ボールがプレーに移されるまでに中立地帯を侵してはならない”というルールによって合理的なブロッキングがみられるに至り、危険緩和に大いに役立った。
5 改革案つづく……1910年(キャンプ退陣)
エール大学のキャンプはパスが初めて許された時にはそれを唱導したにも拘らず、やがてランニング・プレーのための戦略を紹介することに意を注いでフォワード・パスの排除を主張するようになった。この態度は東部の大学がフォワード・パスを軽視し、逆に中西部に於ては次第にパスが有力武器となりつつあったところに理由がありそうである。そしてキャンプのパス排除案はハーバード大学のホートン(Haughton)の称えるパス維持の立場と激しく対立したが、時勢はパスをさらに伸張させる方に味方した。こうして多年にわたってルール委員会を支配してきたキャンプの最高権力もついに終りをつげ、新たな勢力と交代する時期が来た。そして必然的にフォワード・パスを発展させ、マス・プレーを終らせるための種々の施策が取られた。
(1) パス使用に関する制限規則は1910年から1912年に至って全く排除され、今日と同じくスクリメージの後方ならどんな所からも前方へパスを投げることができた。
(2) パス・レシーバーを厳重に保護するルールが1910年に確立された。
(3) ラインマンがバックフィールドに後退することを禁じ、攻撃側のスクリメージ・ラインはつねに7人必要であることを明確にした(1910年)そして手や身体を使ってランナーを押したり引っぱったりすることを禁じ、マス・プレー除去に強い反応を示した。
6 改革案つづく……1912年(恒久策)
フォワード・パスの合法化は1913年のアーミー・ノートルダム戦で実を結び、この年をもって近代フットボール発足の年ということができる。1906年の提案以後、1910年、1912年のルールの変更によってゲームの輪郭は今日の標準と大差ないものとなった。以後も年々、数多くの変更があって戦術的転針を促すことはあったが、根本的には1912年をもってフットボールの標準は確立されたということができる。その恒久案とは
(1) 3ダウンで10ヤードの代りに、4ダウンとする
(2) フィールドは110ヤードから100ヤードとなり、各ゴール・ラインの後に10ヤード幅のエンド・ゾーンが設けられ、エンド・ゾーン内で捕球したフォワード・パスは合法としてTDを認められた。それ以前はゴール・ラインを越えてパスを取るとタッチ・バックであった
(3) フォワード・パスはスクリメージの後方ならどこからでも投げることができた。
(4) キック・オフは55ヤード・ラインの代りに40ヤードに移った。
(5) TDが5点から6点、フィールド・ゴールは4点から3点となった。
以上のすべては恒久的な効果をもつ重要な変更であり、近代フットボールに至る画期的な要因として強く作用した。この恒久案を指導したのはキャンプの後継者としてルール委員会の主宰者となったダートマス大学のホール(Edward K. Hall)であった。
7 アーミー・ノートルダム戦
ルールによって支持されたフォワード・パスの発展に明確な形を与える端緒となったのは1913年のアーミー・ノートルダム戦であった。二流チームのノートルダム大学が驚嘆すべきフォワード・パスの冴えをみせて強大国アーミーを見事に撃破したこの事実はフォワード・パスに関する限り最もセンセーショナルな偉業であるといえる。このゲームはノートルダム大学をして無名の存在から一躍全国的な名声を得させるとともに、攻撃武器としてのフォワード・パスの位置を確立したものであった。
ノートルダム大学の成功は新らしくコーチに就任したハーパー(J. Harper)の才能と、QBドレイス(Gus Dorais)エンドのロックン(Knute Rockne)主将の卓越した技術に追うところが多い。1913年の夏、ドレイスとロックンの二人はオハイオ州の避暑地であるセダーポイント(Cedar Point)で働いていたが、アーミーに対するかすかな自信でも植えつけるために余暇を利用してフォワード・パスの練習に励んだ。そしてシーズンに入るとともに両者のパス・コンビネーションが驚くべき域に達していることをアーミーは知らなかった。アーミーはオール・アメリカ級のスターをそろえ、選手はもとより観客のすべてはノートルダム大学をちょっとした練習相手くらいに考えていたようであった。しかしノートルダム大学はすべてをフォワード・パスに掛けるペースを崩さず、名手ドレイスの絶妙なパスワークはしばしばアーミーの守備陣を棒立ちにさせた。そして最初のTDはドレイス~ロックンのコンビによる40ヤードのパスによって完成された。そのあとアーミーも巨大な力で押してきて2TDを返し、前半を終って得点はノートァ
襯瀬・唄~13アーミーであった。後半アーミーはパスに備えてその守備陣型を変えたが、ドレイスは逆にパスとみせてランニング・プレーを効果的に使い始め、アーミーのラインを随所に破った。そして最後の切札であるパスの威力を要所に織りまぜながら着々と得点を重ねた。得点は35~13、ノートルダム大学の実に見事な勝利であった。フォワード・パスは17回使用して14回の成功、パスによる獲得距離は243ヤード、5つのTDはすべてフォワード・パスの結果であった。こうしてアーミーの古い体当たり戦法は清新溌剌たるノートルダム大学のオープン・プレーに頭を垂れた。フォワード・パスはもう単なる実施可能の一部分というものではなく、攻撃の必須武器となったのである。
8 空中戦時代へ
アーミー・ノートルダム戦の予期せざる結果は従来以上にフットボールを流行させる要因となった。そして体重の少ない選手から成る小さな大学でもフォワード・パスの使用によって結構、大型チームと対抗できることを実証した。
南西部ではオクラホマ大学の台頭が目につく。1914年、オクラホマ大学のコーチ、オーエン(Bennie Owen)は未経験者ぞろいのチームを指導するに当って、根本的にプレーのスタイルを変更し、フォワード・パスに全精力を注いだ。そしてそれまでどのチームも成し得なかったラン・パス均一化に成功し、従来の常識を上回るパス使用によって着々と成果を納めた。この年、オクラホマ大学は1マイルに及ぶパスを成功させ、TDパスは25回、そして9勝1引分という法外の成績を納めた。翌1915年、さらにパスの威力を伸ばしたオクラホマ大学は10勝全勝の記録でシーズンを終了し広く絶賛を博した。オクラホマ大学は毎試合平均30~35回のパスを投げ、フォワード・パスによる獲得距離がいつもランを上回るという徹底したものであった。
1915年のピッツバーグ大学も有名なワーナーの指導でフォワード・パスをマスターし、それまで東部の小さな存在から、一躍選手権チームにのし上がるほどの成長をみせた。その他、モリソン(Ray Morrison)の率いるサザーン・メソジスト(Southern Methodist)大学、ヨストがコーチし、名手フリードマン(Benny Friedman)を擁するミシガン大学を始め、各地でパスを取り上げて脚光を浴びるチームが続出した。こうして空中曲芸的なフットボールの時代がつづき、観客は次第にその魅力に酔いしれていった。
アーカイブ
- 2025年1月(5)
- 2024年12月(3)
- 2024年11月(13)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(6)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(9)
- 2024年5月(11)
- 2024年4月(6)
- 2024年3月(7)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(4)
- 2023年12月(10)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(1)
- 2023年6月(6)
- 2023年5月(6)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(4)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(6)
- 2022年12月(10)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(4)
- 2022年9月(4)
- 2022年8月(3)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(4)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(6)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(9)
- 2021年11月(5)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(4)
- 2021年8月(1)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(7)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(3)
- 2021年2月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(2)
- 2020年9月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年4月(7)
- 2020年3月(2)
- 2020年2月(9)
- 2020年1月(8)
- 2019年12月(12)
- 2019年11月(7)
- 2019年10月(4)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(2)
- 2019年7月(1)
- 2019年6月(5)
- 2019年5月(8)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(8)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(4)
- 2018年12月(11)
- 2018年11月(6)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(4)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(5)
- 2018年5月(5)
- 2018年4月(6)
- 2018年3月(9)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(5)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(6)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(6)
- 2017年2月(4)
- 2017年1月(5)
- 2016年12月(11)
- 2016年11月(7)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(4)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年6月(11)
- 2016年5月(6)
- 2016年4月(4)
- 2016年3月(9)
- 2016年2月(4)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(9)
- 2015年10月(2)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(3)
- 2015年7月(3)
- 2015年6月(7)
- 2015年5月(3)
- 2015年4月(2)
- 2015年3月(8)
- 2015年2月(6)
- 2015年1月(3)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(7)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(3)
- 2014年8月(4)
- 2014年7月(8)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(10)
- 2014年4月(4)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(6)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(10)
- 2013年11月(7)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(3)
- 2013年7月(5)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(5)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(5)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(8)
- 2012年11月(7)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(3)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(7)
- 2012年5月(4)
- 2012年4月(5)
- 2012年3月(6)
- 2012年2月(6)
- 2012年1月(2)
- 2011年12月(8)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(4)
- 2011年9月(4)
- 2011年8月(3)
- 2011年7月(3)
- 2011年6月(6)
- 2011年5月(6)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(9)
- 2011年2月(4)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(6)
- 2010年11月(14)
- 2010年10月(4)
- 2010年9月(3)
- 2010年8月(3)
- 2010年7月(3)
- 2010年6月(6)
- 2010年5月(4)
- 2010年4月(9)
- 2010年3月(7)
- 2010年2月(7)
- 2009年12月(1)
- 2009年11月(2)
- 2009年10月(2)
- 2009年9月(2)
- 2009年8月(4)
- 2009年7月(5)
- 2009年6月(8)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(7)
- 2009年3月(10)
- 2009年2月(3)
- 2009年1月(1)
- 2008年12月(1)
- 2008年11月(4)
- 2008年10月(2)
- 2008年9月(3)
- 2008年8月(2)
- 2008年7月(1)
- 2008年6月(5)
- 2008年5月(2)
- 2008年4月(4)
- 2008年3月(6)
- 2008年2月(1)
- 2008年1月(6)
- 2007年12月(2)
- 2007年11月(2)
- 2007年10月(2)
- 2007年9月(3)
- 2007年8月(4)
- 2007年7月(5)
- 2007年6月(8)
- 2007年5月(5)
- 2007年4月(9)
- 2007年3月(11)
- 2007年2月(3)
- 2007年1月(6)
- 2006年12月(3)
- 2006年11月(3)
- 2006年10月(4)
- 2006年9月(2)
- 2006年8月(7)
- 2006年7月(3)
- 2006年6月(7)
- 2006年5月(6)
- 2006年4月(6)
- 2006年3月(6)
- 2006年2月(3)
- 2006年1月(3)
- 2005年12月(1)
- 2005年11月(2)
- 2005年10月(3)
- 2005年9月(2)
- 2005年8月(8)
- 2005年7月(1)
- 2005年6月(4)
- 2005年5月(6)
- 2005年4月(6)
- 2005年3月(6)
- 2005年2月(4)
- 2005年1月(3)
- 2004年12月(1)
- 2004年11月(2)
- 2004年10月(3)
- 2004年9月(3)
- 2004年8月(2)
- 2004年7月(2)
- 2004年6月(3)
- 2004年5月(3)
- 2004年4月(4)
- 2004年3月(10)
- 2004年2月(1)
- 2004年1月(4)
- 2003年11月(3)
- 2003年10月(2)
- 2003年9月(3)
- 2003年8月(16)
- 2003年7月(1)
- 2003年6月(5)
- 2003年5月(3)
- 2003年4月(4)
- 2003年3月(8)
- 2003年2月(4)
- 2003年1月(3)
- 2002年11月(3)
- 2002年10月(2)
- 2002年9月(3)
- 2002年8月(2)
- 2002年7月(3)
- 2002年6月(5)
- 2002年5月(5)
- 2002年4月(4)
- 2002年3月(6)
- 2002年2月(6)
- 2002年1月(6)
- 2001年12月(4)
- 2001年11月(2)
- 2001年10月(4)
- 2001年9月(3)
- 2001年8月(2)
- 2001年7月(5)
- 2001年6月(5)
- 2001年5月(3)
- 2001年4月(4)
- 2001年3月(14)
- 2001年2月(3)
- 2001年1月(2)
- 2000年12月(2)
- 2000年11月(2)
- 2000年10月(4)
- 2000年9月(3)
- 2000年8月(3)
- 2000年7月(6)
- 2000年6月(3)
- 2000年5月(3)
- 2000年4月(3)
- 2000年3月(5)
- 2000年2月(4)
- 2000年1月(5)
- 1999年12月(4)
- 1999年11月(3)
- 1999年10月(2)
- 1999年9月(3)
- 1999年8月(1)
- 1999年7月(3)
- 1999年6月(3)
- 1999年5月(6)
- 1999年4月(4)
- 1999年3月(5)
- 1999年1月(3)
- 1997年12月(3)
- 1997年11月(2)
- 1997年10月(2)
- 1997年9月(3)
- 1997年8月(1)
- 1997年7月(2)
- 1997年6月(8)
- 1997年5月(5)
- 1997年4月(4)
- 1997年3月(4)
- 1997年2月(1)
- 1997年1月(3)
- 1991年2月(6)
- 1959年2月(11)