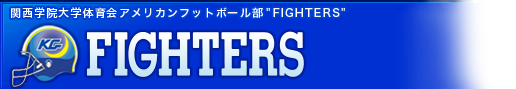米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
第7章 フォーメイション・フットボールの推移
1959/02/28
フォーワード・パスが新しい武器として取り上げられ、フットボールの攻撃型を実質的に変化させる動きの見え始めたころ、攻撃型に強い影響を与える二つの重要なものが発達してきた。その第一はウィング・バック・フォーメイション(wingback formation)であり、第二は(shift)である。前者は以後の攻撃型の標準を確立したものであり、後者も攻撃型に強い支配力を見せたが、これは以後の規則制限によって次第に衰微していった。ここでは最初のオールドTに始まり、マス・プレーの動乱期を経て明確なフォーメイション時代に入った過程・及びその後現在までの攻撃型の変遷をたどってみる。
フットボールの特徴の一つとして攻守の判然たる区分が挙げられる。そのため攻守両局面を独立するものとして研究し、攻めれば得点の追求、守れば失点の防止を目的として激しく攻守が争い、そこに攻撃型、守備型の展開がみられた。
攻撃型の最初のものはTであり、ついでエンド・バック、ガード・バック、タックル・バックなどが1890年代に流行をみせたが、これらはいずれもマス・プレー時代の原始的なフォーメイションであった。この時代のフットボールは専ら力の闘争であり、攻撃側はまずフライング・スタートによって守備力を抑えつけようとし、これが禁じられるとラインの人員に制限がないところから、バックフィールドの人員を増やすことによって集中的な力を守備側にぶっつけることを考えた。これに対し守備側も力には力をもって応じたため、故障者続出の物凄いフットボール時代を生んだ。実質的にはフォーメイションそのものの妙味はみられないが、このマス・プレーをもって第一期のフットボール時代と名付けてよかろう。
1906年にフォーワード・パスが合法となり、1910年にラインの7人制が規定されたときから本格的なフォーメイション・フットボールの時代が始まるといってよい。その第一段階はシングル・ウィング(single wing)とボックス・フォーメイションの時代である。この時代に於いても最初はマス・プレーの名残をとどめ、バックスがくさび型になって強引な突破プレーに頼ったものだが、次第に外側へ迂回する攻撃方法が各チームの狙いとなっていった。これに対し守備側はオーバーシフト(overshift)の研究によってオープン攻撃を封じようと試み、逆に守備が攻撃を上回る一時期を招いた。ために攻撃側はリバース・プレー(reverse play)の活用、パス、パントの可能性をウィングバック、ボックス各フォーメイションに織りこむなど、その多角的な機動力にモノいわせようとし、第二期のフォーメイション・フットボール時代は1910年から約30年、いわゆるフットボールの黄金期を大いににぎわせたのであった。
1940年に入ってモダーンTの成功がそれ以前のフットボールに革命をもたらした。スピードとタイミングを生命とするTフォーメイションは最初QBから他のバックにハンド・オフ(hand off)するライン突破プレーを確実な稼ぎ手としていたが、これが段階守備法(offset defense)の研究によって効果を減じると、今度はハンド・オフ・プレーを囮としてまたも大きくオープンを狙うように変わっていった。最初の型通りのタイトTからスプレッドT(spread T)フランカーT(flanker T)スプリットT(split T)に移っていった過程はいずれもこの推移を物語っている。
現代のフットボールは左右に大きく移動するスウィンギング・フットボール(swinging football)の時代であるといわれる。しかも近時の傾向としてパス重点策が取られているところからみて、攻撃側はフィールドを一ぱいに使った広範な動きで守備を乱そうとする。従って守備側も勢い広く散開することを余儀なくされた。現代は明らかに攻撃力が守備力を上回る得点力豊かな時代であるといってよかろう。
1880年、スクリメージの創設とともにボールをプレーに移すクォーターバック(QB)がゲームの中に姿を現した。それまでのラグビー式スクラムでは、両方のラッシャーズの間にボールを投げ入れ、互いに靴で後ろに蹴って味方のバックに送ろうとしたものであったが、このスクリメージの手続きによってボールをプレーに移す方法が確立された。そのため攻撃チームは進んでプレーを組み立てることができ、このオールドT型からVトリック、ウェッジなど物凄いマス・プレーを繰り出したものであった。1880年から約10年間はこのオールドTがきまった攻撃型となり、ラインは完全なバランスをもって相手のラインと正面から対峙し、バックスは今日のT型より遙かに深い位置でプレーしていた。
1888年にロー・タックル(low tackle)の規制があり、ブロッキングの合法化が認められて、バックフィールドがラインに接近してプレーするようになるとともに従来のマス・プレーを上回り、さらにフライングを伴う破壊的な肉体闘争の時代となる。その最初の攻撃型がこのエンズ・バックであり、1890年、エール大学を出たスタッグ(A. A. Stagg)がスプリングフィールド・カレッジで初めて教えた。当時のルールではラインの人員に制限がなかったので、両方のエンドを後退させてバックフィールドの力を増強させようと狙ったものであり、以後数年の流行をみるようになった。
スタッグはエンドをラインから約2ヤード後方で、ほとんどQBと同じ線上に下げ、プレーによって少しずつその位置を変えさせた。このエンドの動きは
(1) ボールを持ってオフ・タックルやオープンへの効果的なランナーとして
(2) バックスが中央またはオープンを衝く時のブロッカーまたは援護走者として
(3) エンドが加わって行なう新しいクリス・クロス・プレー(criss-cross play)のキー・マンとして
実に多方面に及んだ。
1893年になるとプリンストン大学もこのエンズ・バックを効果的に使い、キング(Philip King)がエンドをラインから2.5ヤード下げ、タックルの外側に配置して完全な一連のプレーを作り出した。
1894年にVトリック、フライング・ウェッジなどの惰性をつけたマス・プレーを無効とする改革があったが、そのルールに接触せずに物凄い威力を示すものとしてペンシルヴァニア大学のコーチ、ウッドラフ(G. Woodruff)が創造したのがこのガーズ・バックであった。ウッドラフは1894年の対プリンストン戦で初めてこのフォーメイションを使い、その絶対的な破壊力は忽ちのうちに遠く広くフットボール界にセンセーションを巻き起こした。そして以後ハーバード大学がその防止策を工夫するまで約6年間はガーズ・バックの時代がつづいた。このフォーメイションは2人のガードをラインからバックフィールドに下げ、中央といわずオープンといわず、ライン各所を自在に衝く機動性をガードに持たせたために非常に強力なものとなった。しかしこのプレーがまた負傷を多く伴うところからついに1910年の改革案に於て無効として葬られた。
1894年、スタッグはシカゴ大学でタックルズ・バック・フォーメイションを発明した。これは同年11月29日、感謝祭の日の対ミシガン戦で初めて用い、2人のタックルをそれぞれガードの後方2~2.5ヤードの所に位置させ主として相手のタックルの内側を狙って成功した。このプレーは1890年のエンズ・バックと同系のものであった。
一方、ウッドラフのガーズ・バックに強い影響を受けたウィリアムス博士は1900年にミネソタ大学にやってくるとタックルを1人だけバックフィールドに下げる新しい型のフォーメイションを創案して大いに効果をあげた。このプレーは早速エール大学にも取り入れられ、キャンプ・コーチの手によって完成された。そしてこの型のタックル・バックもまた暫時フットボール界を支配する強力な武器となったが、ついに1910年、ラインからバックフィールドに後退して位置することを禁じ、ライン7人制が明確に規定されるとともにその働きも終わった。
1910年のルール変更によってラインの7人制がきまり、またマス・プレーの使用が禁じられると、バックフィールドに於て力を集中する方法はなくなり、今度はバックスの有効な配列が問題となってきた。1912年、キャリッスル大学のコーチ・ワーナー(Glen Warner)はシングル・ウィングという新しい攻撃型を作り出し、ついでダブル・ウィングを生み出して本格的なフォーメイション・フットボール時代の先鞭をつけた。当時守備側のタックルは大概攻撃側エンドの外側に位置していたため、オープン・プレーの時にそのタックルをブロックするのが大へん厄介な仕事であった。そこでワーナーはバックの1人を相手のタックルの外側に置くアイディアを考え、初めて1912年の対アーミー戦に用いて快勝の直接因となった。これがモダーン・シングル・ウィングの前駆としてZフォーメイションと呼ばれるものであり、ラインは左右アンバランスであった。この戦法はとくにストロング・サイドへの早いオープンの展開を可能にしたが、それに対抗するため守備側がラインをずらしてオープン攻撃を阻止すると、今度はショート・サイドへのリバース・プレーを発達させる結果となった。
1920年代にノートルダム大学がTから一種のシングル・ウィングにシフトする攻撃法を軌道に乗せ、以後10数年ロックン(Knute Rockne)の指導によって一時期を画した。すなわちノートルダム・ボックスの全盛期である。これについては次の機会に詳述する。
シングル・ウィングからのリバース・プレーが次第にマークされるようになると、ショート・サイドのタックルをブロックすることが難しくなり、その効果を段々と減じてきた。そこでこのタックルをブロックする必要がダブル・ウィングの発達をうながすことになった。ワーナーが創始したこの攻撃の最初のものはAフォーメイションと呼ばれ、ラインはタイトであり、アンバランスであった。この攻法は本質的にはパワー・フォーメイションであり、とくに優秀なFBを擁した時に効果があったが、またスピンやリバースを使った変化プレー、パス・プレー、ラトラル・プレーにも強力な持味を持っていた。
このAフォーメイションから用いられた3つの攻撃サイクルは
(ⅰ) FBがLHにボールを渡すか、キープするか、またはRHにボールを渡す3つの組み合わせで、キープの時は相手のタックルの位置を衝き、どちらかのHBに渡す時はともにオープンを狙った。こうしたリバース・プレーの狙いはシングル・ウィングと同系のものであり、それをさらに高度に発達させたものであった。
(ⅱ) FBがRHにボールを渡すか、キープするかLHに渡すか、3種の組み合わせであり、このサイクルの妙味はFBがキープして一回転したままLHに前でのハンド・オフを行なうところにあり、FB自らも有効な援護走者として働くことができた。
(ⅲ) FBの強引なライン突破プレーを基礎とし、これにラトラル・プレーを組み合わせて有効なオープンへの転換を狙ったものである。ラトラルの時にはFBがどちらかのタックルにボールを渡しHBまたはエンドにラトラルを送ってオープンを衝いた。
Aフォーメイションの発達した形がBフォーメイションであり、FBはAよりも深く約5ヤード後方で、パス及びクィック・キックに適した位置についた。この攻法からAと全く同じ狙いで各種のプレーが繰り出されたがQBがラインとFBの中間に位置してこの攻法のキー・マンとなっているのが注目される。
さらにダブル・ウィングはBからCフォーメイションへと進んでいった。これは両エンド及び両ウィングバックを広く位置せしめることによってプレーの行動範囲を著るしく拡大し、とくに最良のパス・フォーメイションとして絶大なる威力を示した。
ウィング・バック・システムの流行はフットボールの発展に一時期を画するものであった。このシステムを作りだしたワーナーのアイディアはスタッグのエンド・バック、及びワーナー自身がコーネル大学の主将時代にニューエル(Newell)コーチに指導されたエンド・バックに影響を受けたものである。
彼のウィング・バックの原理は
(1) ウィング・バックが両サイドの守備側タックルに適切なブロッキングの角度を得ること
(2) 守備ライン全体をオーバーシフトさせないこと
(3) ラインをプルアウトに出す時、クロス・チェック(cross check)が可能なようにアンバランス・ラインを用いること
(4) ラインを安全にプルアウトさせるためエンドからエンドまでをタイトにすること
(5) 縦へのパワーな突進、ウィング・バックを使っての横の変化に富んだ動き、及びパス、パントの可能性など各種の機動力を有すること
などであった。
ワーナーは1913年にキャリッスル大学で初めてダブル・ウィング・バックを案出したのちスタンフォード大学に転じたが、以後も改良を重ね、1928年、アーミーとの大試合に於てその完成された妙味を示した。その時まで最も流行した攻撃法は標準的なTフォーメイションからシフトするノートルダム・ボックスとシングル・ウィングであったが、翌1929年にはダブル・ウィングが全米を席巻する勢いであった。この年、ケル(Andy Kerr)はコルゲート(Colgate)大学で大成功を納め、ひきつづき数年は強豪の名をほしいままにした。
1928年、ブラウン大学のコーチ、マックローリィ(D. O. McLaughry)がワーナーのシステムに改良を加えてトリプル・ウィングを初めて使用した。そしてその年、強豪コルゲート大学を破る殊勲を立て、つづく5年間はその卓越したパス・ラン両面の可能性を示した。
スクリメージ設定以前のフットボールの原始時代は殆ど深いパント・フォーメイションからキックを多用していたが、当時は直接センターからキッカーへボールを送るやり方はみられず、QBがその中継者となっていた。直接のスナップ・バックが用いられたのはやっと1895~1896年のことであり、その発案者スタッグが直ちにこのショート・パントフォーメイションとクィック・キックを紹介している。そして1910年、1920年代にはこのフォーメイションからキック、パス、ランの変化をみせるようになった。ハーバード大学のホートン(P. Haughton)ミシガン大学のヨスト(Fielding Yost)らもこれに着眼している。
パント・フォーメイションの変形としてラインの間隔をひろげたスプレッド・パントが1910年代にスプリングフィールドのコーチをしたマッカーディ(J. H. Mccurdy)及びアーカンソー大学のベズデック(H. Bezdek)によって取り上げられた。パンターはセンターから13~15ヤードもさがり、パンターを守る者は2人のバックだけであり、他の全員はボールのスナップと同時にパントのカバーに飛び出して大いに効果をあげた。同時にこの広範囲な配列から守備を拡げたのち、パス、ランを織りまぜる機動性もみられた。このシステムは優秀なセンターの存在が決定的なカギとなるものであり、1940年代に入って多くのチームがこれを取り上げるとともに優秀なセンターを生んでいった。1916年、ズプク(Zuppke)の率いるイリノイ大学が強豪ミネソタ大学を破ったのもこのスプレッド・パントの威力であり、最近ではテキサス・クリスチャン大学のメーヤー(D. Meyer)がこのシステムの第一人者として有名である。
1922年、サザーン・メソジスト大学ではモリソン・コーチがYフォーメイションを作った。この攻法の特徴は4人のバックスがY字型に並んで、いずれも直接センターからのスナップ・ボールを取れる位置にあることであった。モリソンはこのYフォーメイションとショート・パント・フォーメイションを併用して1923年、1926年に地区の覇権を得ている。
降って1941年にシラキュース大学のソレム(O. Solem)コーチが別種のYフォーメイションを紹介した。この方法ではバックスの配置はモリソンの作ったものと大差なかったが、センターがスクリメージに背中を向けて反対になり、バックの方を向いてボールをパスするものであった。このためセンターは直接バックに広くボールを送ることができバックの活動範囲を著るしく拡大した。翌1942年、ルール委員会はこの反対向きのセンターの妥当性を検討した結果、これを公正でないとして禁止した。
1940年代に入るとともにウィング・バックの時代は一転して、スピードとタイミングを生命とするモダーンTの時代に入る。フットボールのそもそもの最初に基本的なフォーメイションであったTが結局現代のフットボールを支配するものとして返り咲いたのである。このモダーンTについてはつぎの機会に記することにする。
1949年、ヴァージニア軍官学校(Virginia Military Institute)のコーチ、ヌージェント(Tom Nugent)が発明し、1951年には突如、名門ノートルダム大学が再び採用して話題をまいた。このシステムではQBはノーマルTの位置にあり、その後にFB、RH、LHの順で1列に配置され、バックスがすべて同じ所からスタートするため守備陣を混乱させる効があった。
1 攻撃型の変遷
フットボールの特徴の一つとして攻守の判然たる区分が挙げられる。そのため攻守両局面を独立するものとして研究し、攻めれば得点の追求、守れば失点の防止を目的として激しく攻守が争い、そこに攻撃型、守備型の展開がみられた。
攻撃型の最初のものはTであり、ついでエンド・バック、ガード・バック、タックル・バックなどが1890年代に流行をみせたが、これらはいずれもマス・プレー時代の原始的なフォーメイションであった。この時代のフットボールは専ら力の闘争であり、攻撃側はまずフライング・スタートによって守備力を抑えつけようとし、これが禁じられるとラインの人員に制限がないところから、バックフィールドの人員を増やすことによって集中的な力を守備側にぶっつけることを考えた。これに対し守備側も力には力をもって応じたため、故障者続出の物凄いフットボール時代を生んだ。実質的にはフォーメイションそのものの妙味はみられないが、このマス・プレーをもって第一期のフットボール時代と名付けてよかろう。
1906年にフォーワード・パスが合法となり、1910年にラインの7人制が規定されたときから本格的なフォーメイション・フットボールの時代が始まるといってよい。その第一段階はシングル・ウィング(single wing)とボックス・フォーメイションの時代である。この時代に於いても最初はマス・プレーの名残をとどめ、バックスがくさび型になって強引な突破プレーに頼ったものだが、次第に外側へ迂回する攻撃方法が各チームの狙いとなっていった。これに対し守備側はオーバーシフト(overshift)の研究によってオープン攻撃を封じようと試み、逆に守備が攻撃を上回る一時期を招いた。ために攻撃側はリバース・プレー(reverse play)の活用、パス、パントの可能性をウィングバック、ボックス各フォーメイションに織りこむなど、その多角的な機動力にモノいわせようとし、第二期のフォーメイション・フットボール時代は1910年から約30年、いわゆるフットボールの黄金期を大いににぎわせたのであった。
1940年に入ってモダーンTの成功がそれ以前のフットボールに革命をもたらした。スピードとタイミングを生命とするTフォーメイションは最初QBから他のバックにハンド・オフ(hand off)するライン突破プレーを確実な稼ぎ手としていたが、これが段階守備法(offset defense)の研究によって効果を減じると、今度はハンド・オフ・プレーを囮としてまたも大きくオープンを狙うように変わっていった。最初の型通りのタイトTからスプレッドT(spread T)フランカーT(flanker T)スプリットT(split T)に移っていった過程はいずれもこの推移を物語っている。
現代のフットボールは左右に大きく移動するスウィンギング・フットボール(swinging football)の時代であるといわれる。しかも近時の傾向としてパス重点策が取られているところからみて、攻撃側はフィールドを一ぱいに使った広範な動きで守備を乱そうとする。従って守備側も勢い広く散開することを余儀なくされた。現代は明らかに攻撃力が守備力を上回る得点力豊かな時代であるといってよかろう。
2 オールドT(old T)
1880年、スクリメージの創設とともにボールをプレーに移すクォーターバック(QB)がゲームの中に姿を現した。それまでのラグビー式スクラムでは、両方のラッシャーズの間にボールを投げ入れ、互いに靴で後ろに蹴って味方のバックに送ろうとしたものであったが、このスクリメージの手続きによってボールをプレーに移す方法が確立された。そのため攻撃チームは進んでプレーを組み立てることができ、このオールドT型からVトリック、ウェッジなど物凄いマス・プレーを繰り出したものであった。1880年から約10年間はこのオールドTがきまった攻撃型となり、ラインは完全なバランスをもって相手のラインと正面から対峙し、バックスは今日のT型より遙かに深い位置でプレーしていた。
3 エンズ・バック(ends back)
1888年にロー・タックル(low tackle)の規制があり、ブロッキングの合法化が認められて、バックフィールドがラインに接近してプレーするようになるとともに従来のマス・プレーを上回り、さらにフライングを伴う破壊的な肉体闘争の時代となる。その最初の攻撃型がこのエンズ・バックであり、1890年、エール大学を出たスタッグ(A. A. Stagg)がスプリングフィールド・カレッジで初めて教えた。当時のルールではラインの人員に制限がなかったので、両方のエンドを後退させてバックフィールドの力を増強させようと狙ったものであり、以後数年の流行をみるようになった。
スタッグはエンドをラインから約2ヤード後方で、ほとんどQBと同じ線上に下げ、プレーによって少しずつその位置を変えさせた。このエンドの動きは
(1) ボールを持ってオフ・タックルやオープンへの効果的なランナーとして
(2) バックスが中央またはオープンを衝く時のブロッカーまたは援護走者として
(3) エンドが加わって行なう新しいクリス・クロス・プレー(criss-cross play)のキー・マンとして
実に多方面に及んだ。
1893年になるとプリンストン大学もこのエンズ・バックを効果的に使い、キング(Philip King)がエンドをラインから2.5ヤード下げ、タックルの外側に配置して完全な一連のプレーを作り出した。
4 ガーズ・バック(guards back)
1894年にVトリック、フライング・ウェッジなどの惰性をつけたマス・プレーを無効とする改革があったが、そのルールに接触せずに物凄い威力を示すものとしてペンシルヴァニア大学のコーチ、ウッドラフ(G. Woodruff)が創造したのがこのガーズ・バックであった。ウッドラフは1894年の対プリンストン戦で初めてこのフォーメイションを使い、その絶対的な破壊力は忽ちのうちに遠く広くフットボール界にセンセーションを巻き起こした。そして以後ハーバード大学がその防止策を工夫するまで約6年間はガーズ・バックの時代がつづいた。このフォーメイションは2人のガードをラインからバックフィールドに下げ、中央といわずオープンといわず、ライン各所を自在に衝く機動性をガードに持たせたために非常に強力なものとなった。しかしこのプレーがまた負傷を多く伴うところからついに1910年の改革案に於て無効として葬られた。
5 タックル・バック(tackle back)
1894年、スタッグはシカゴ大学でタックルズ・バック・フォーメイションを発明した。これは同年11月29日、感謝祭の日の対ミシガン戦で初めて用い、2人のタックルをそれぞれガードの後方2~2.5ヤードの所に位置させ主として相手のタックルの内側を狙って成功した。このプレーは1890年のエンズ・バックと同系のものであった。
一方、ウッドラフのガーズ・バックに強い影響を受けたウィリアムス博士は1900年にミネソタ大学にやってくるとタックルを1人だけバックフィールドに下げる新しい型のフォーメイションを創案して大いに効果をあげた。このプレーは早速エール大学にも取り入れられ、キャンプ・コーチの手によって完成された。そしてこの型のタックル・バックもまた暫時フットボール界を支配する強力な武器となったが、ついに1910年、ラインからバックフィールドに後退して位置することを禁じ、ライン7人制が明確に規定されるとともにその働きも終わった。
6 シングル・ウィング・バック(single wing back)
1910年のルール変更によってラインの7人制がきまり、またマス・プレーの使用が禁じられると、バックフィールドに於て力を集中する方法はなくなり、今度はバックスの有効な配列が問題となってきた。1912年、キャリッスル大学のコーチ・ワーナー(Glen Warner)はシングル・ウィングという新しい攻撃型を作り出し、ついでダブル・ウィングを生み出して本格的なフォーメイション・フットボール時代の先鞭をつけた。当時守備側のタックルは大概攻撃側エンドの外側に位置していたため、オープン・プレーの時にそのタックルをブロックするのが大へん厄介な仕事であった。そこでワーナーはバックの1人を相手のタックルの外側に置くアイディアを考え、初めて1912年の対アーミー戦に用いて快勝の直接因となった。これがモダーン・シングル・ウィングの前駆としてZフォーメイションと呼ばれるものであり、ラインは左右アンバランスであった。この戦法はとくにストロング・サイドへの早いオープンの展開を可能にしたが、それに対抗するため守備側がラインをずらしてオープン攻撃を阻止すると、今度はショート・サイドへのリバース・プレーを発達させる結果となった。
7 ノートルダム・ボックス(Notre Dame Box)
1920年代にノートルダム大学がTから一種のシングル・ウィングにシフトする攻撃法を軌道に乗せ、以後10数年ロックン(Knute Rockne)の指導によって一時期を画した。すなわちノートルダム・ボックスの全盛期である。これについては次の機会に詳述する。
8 ダブル・ウィング・バック(double wing back)
シングル・ウィングからのリバース・プレーが次第にマークされるようになると、ショート・サイドのタックルをブロックすることが難しくなり、その効果を段々と減じてきた。そこでこのタックルをブロックする必要がダブル・ウィングの発達をうながすことになった。ワーナーが創始したこの攻撃の最初のものはAフォーメイションと呼ばれ、ラインはタイトであり、アンバランスであった。この攻法は本質的にはパワー・フォーメイションであり、とくに優秀なFBを擁した時に効果があったが、またスピンやリバースを使った変化プレー、パス・プレー、ラトラル・プレーにも強力な持味を持っていた。
このAフォーメイションから用いられた3つの攻撃サイクルは
(ⅰ) FBがLHにボールを渡すか、キープするか、またはRHにボールを渡す3つの組み合わせで、キープの時は相手のタックルの位置を衝き、どちらかのHBに渡す時はともにオープンを狙った。こうしたリバース・プレーの狙いはシングル・ウィングと同系のものであり、それをさらに高度に発達させたものであった。
(ⅱ) FBがRHにボールを渡すか、キープするかLHに渡すか、3種の組み合わせであり、このサイクルの妙味はFBがキープして一回転したままLHに前でのハンド・オフを行なうところにあり、FB自らも有効な援護走者として働くことができた。
(ⅲ) FBの強引なライン突破プレーを基礎とし、これにラトラル・プレーを組み合わせて有効なオープンへの転換を狙ったものである。ラトラルの時にはFBがどちらかのタックルにボールを渡しHBまたはエンドにラトラルを送ってオープンを衝いた。
Aフォーメイションの発達した形がBフォーメイションであり、FBはAよりも深く約5ヤード後方で、パス及びクィック・キックに適した位置についた。この攻法からAと全く同じ狙いで各種のプレーが繰り出されたがQBがラインとFBの中間に位置してこの攻法のキー・マンとなっているのが注目される。
さらにダブル・ウィングはBからCフォーメイションへと進んでいった。これは両エンド及び両ウィングバックを広く位置せしめることによってプレーの行動範囲を著るしく拡大し、とくに最良のパス・フォーメイションとして絶大なる威力を示した。
9 ダブル・ウィング・バックの原理
ウィング・バック・システムの流行はフットボールの発展に一時期を画するものであった。このシステムを作りだしたワーナーのアイディアはスタッグのエンド・バック、及びワーナー自身がコーネル大学の主将時代にニューエル(Newell)コーチに指導されたエンド・バックに影響を受けたものである。
彼のウィング・バックの原理は
(1) ウィング・バックが両サイドの守備側タックルに適切なブロッキングの角度を得ること
(2) 守備ライン全体をオーバーシフトさせないこと
(3) ラインをプルアウトに出す時、クロス・チェック(cross check)が可能なようにアンバランス・ラインを用いること
(4) ラインを安全にプルアウトさせるためエンドからエンドまでをタイトにすること
(5) 縦へのパワーな突進、ウィング・バックを使っての横の変化に富んだ動き、及びパス、パントの可能性など各種の機動力を有すること
などであった。
ワーナーは1913年にキャリッスル大学で初めてダブル・ウィング・バックを案出したのちスタンフォード大学に転じたが、以後も改良を重ね、1928年、アーミーとの大試合に於てその完成された妙味を示した。その時まで最も流行した攻撃法は標準的なTフォーメイションからシフトするノートルダム・ボックスとシングル・ウィングであったが、翌1929年にはダブル・ウィングが全米を席巻する勢いであった。この年、ケル(Andy Kerr)はコルゲート(Colgate)大学で大成功を納め、ひきつづき数年は強豪の名をほしいままにした。
10 トリプル・ウィング・バック(triple wing back)
1928年、ブラウン大学のコーチ、マックローリィ(D. O. McLaughry)がワーナーのシステムに改良を加えてトリプル・ウィングを初めて使用した。そしてその年、強豪コルゲート大学を破る殊勲を立て、つづく5年間はその卓越したパス・ラン両面の可能性を示した。
11 ショート・パント(short punt)
スクリメージ設定以前のフットボールの原始時代は殆ど深いパント・フォーメイションからキックを多用していたが、当時は直接センターからキッカーへボールを送るやり方はみられず、QBがその中継者となっていた。直接のスナップ・バックが用いられたのはやっと1895~1896年のことであり、その発案者スタッグが直ちにこのショート・パントフォーメイションとクィック・キックを紹介している。そして1910年、1920年代にはこのフォーメイションからキック、パス、ランの変化をみせるようになった。ハーバード大学のホートン(P. Haughton)ミシガン大学のヨスト(Fielding Yost)らもこれに着眼している。
12 スプレッド・パント(spread punt)
パント・フォーメイションの変形としてラインの間隔をひろげたスプレッド・パントが1910年代にスプリングフィールドのコーチをしたマッカーディ(J. H. Mccurdy)及びアーカンソー大学のベズデック(H. Bezdek)によって取り上げられた。パンターはセンターから13~15ヤードもさがり、パンターを守る者は2人のバックだけであり、他の全員はボールのスナップと同時にパントのカバーに飛び出して大いに効果をあげた。同時にこの広範囲な配列から守備を拡げたのち、パス、ランを織りまぜる機動性もみられた。このシステムは優秀なセンターの存在が決定的なカギとなるものであり、1940年代に入って多くのチームがこれを取り上げるとともに優秀なセンターを生んでいった。1916年、ズプク(Zuppke)の率いるイリノイ大学が強豪ミネソタ大学を破ったのもこのスプレッド・パントの威力であり、最近ではテキサス・クリスチャン大学のメーヤー(D. Meyer)がこのシステムの第一人者として有名である。
13 Yフォーメイション
1922年、サザーン・メソジスト大学ではモリソン・コーチがYフォーメイションを作った。この攻法の特徴は4人のバックスがY字型に並んで、いずれも直接センターからのスナップ・ボールを取れる位置にあることであった。モリソンはこのYフォーメイションとショート・パント・フォーメイションを併用して1923年、1926年に地区の覇権を得ている。
降って1941年にシラキュース大学のソレム(O. Solem)コーチが別種のYフォーメイションを紹介した。この方法ではバックスの配置はモリソンの作ったものと大差なかったが、センターがスクリメージに背中を向けて反対になり、バックの方を向いてボールをパスするものであった。このためセンターは直接バックに広くボールを送ることができバックの活動範囲を著るしく拡大した。翌1942年、ルール委員会はこの反対向きのセンターの妥当性を検討した結果、これを公正でないとして禁止した。
14 モダーンT(modern T)
1940年代に入るとともにウィング・バックの時代は一転して、スピードとタイミングを生命とするモダーンTの時代に入る。フットボールのそもそもの最初に基本的なフォーメイションであったTが結局現代のフットボールを支配するものとして返り咲いたのである。このモダーンTについてはつぎの機会に記することにする。
15 IフォーメイションまたはトルーT(true T)
1949年、ヴァージニア軍官学校(Virginia Military Institute)のコーチ、ヌージェント(Tom Nugent)が発明し、1951年には突如、名門ノートルダム大学が再び採用して話題をまいた。このシステムではQBはノーマルTの位置にあり、その後にFB、RH、LHの順で1列に配置され、バックスがすべて同じ所からスタートするため守備陣を混乱させる効があった。
アーカイブ
- 2025年1月(5)
- 2024年12月(3)
- 2024年11月(13)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(6)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(9)
- 2024年5月(11)
- 2024年4月(6)
- 2024年3月(7)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(4)
- 2023年12月(10)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(1)
- 2023年6月(6)
- 2023年5月(6)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(4)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(6)
- 2022年12月(10)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(4)
- 2022年9月(4)
- 2022年8月(3)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(4)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(6)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(9)
- 2021年11月(5)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(4)
- 2021年8月(1)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(7)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(3)
- 2021年2月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(2)
- 2020年9月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年4月(7)
- 2020年3月(2)
- 2020年2月(9)
- 2020年1月(8)
- 2019年12月(12)
- 2019年11月(7)
- 2019年10月(4)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(2)
- 2019年7月(1)
- 2019年6月(5)
- 2019年5月(8)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(8)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(4)
- 2018年12月(11)
- 2018年11月(6)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(4)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(5)
- 2018年5月(5)
- 2018年4月(6)
- 2018年3月(9)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(5)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(6)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(6)
- 2017年2月(4)
- 2017年1月(5)
- 2016年12月(11)
- 2016年11月(7)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(4)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年6月(11)
- 2016年5月(6)
- 2016年4月(4)
- 2016年3月(9)
- 2016年2月(4)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(9)
- 2015年10月(2)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(3)
- 2015年7月(3)
- 2015年6月(7)
- 2015年5月(3)
- 2015年4月(2)
- 2015年3月(8)
- 2015年2月(6)
- 2015年1月(3)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(7)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(3)
- 2014年8月(4)
- 2014年7月(8)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(10)
- 2014年4月(4)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(6)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(10)
- 2013年11月(7)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(3)
- 2013年7月(5)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(5)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(5)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(8)
- 2012年11月(7)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(3)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(7)
- 2012年5月(4)
- 2012年4月(5)
- 2012年3月(6)
- 2012年2月(6)
- 2012年1月(2)
- 2011年12月(8)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(4)
- 2011年9月(4)
- 2011年8月(3)
- 2011年7月(3)
- 2011年6月(6)
- 2011年5月(6)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(9)
- 2011年2月(4)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(6)
- 2010年11月(14)
- 2010年10月(4)
- 2010年9月(3)
- 2010年8月(3)
- 2010年7月(3)
- 2010年6月(6)
- 2010年5月(4)
- 2010年4月(9)
- 2010年3月(7)
- 2010年2月(7)
- 2009年12月(1)
- 2009年11月(2)
- 2009年10月(2)
- 2009年9月(2)
- 2009年8月(4)
- 2009年7月(5)
- 2009年6月(8)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(7)
- 2009年3月(10)
- 2009年2月(3)
- 2009年1月(1)
- 2008年12月(1)
- 2008年11月(4)
- 2008年10月(2)
- 2008年9月(3)
- 2008年8月(2)
- 2008年7月(1)
- 2008年6月(5)
- 2008年5月(2)
- 2008年4月(4)
- 2008年3月(6)
- 2008年2月(1)
- 2008年1月(6)
- 2007年12月(2)
- 2007年11月(2)
- 2007年10月(2)
- 2007年9月(3)
- 2007年8月(4)
- 2007年7月(5)
- 2007年6月(8)
- 2007年5月(5)
- 2007年4月(9)
- 2007年3月(11)
- 2007年2月(3)
- 2007年1月(6)
- 2006年12月(3)
- 2006年11月(3)
- 2006年10月(4)
- 2006年9月(2)
- 2006年8月(7)
- 2006年7月(3)
- 2006年6月(7)
- 2006年5月(6)
- 2006年4月(6)
- 2006年3月(6)
- 2006年2月(3)
- 2006年1月(3)
- 2005年12月(1)
- 2005年11月(2)
- 2005年10月(3)
- 2005年9月(2)
- 2005年8月(8)
- 2005年7月(1)
- 2005年6月(4)
- 2005年5月(6)
- 2005年4月(6)
- 2005年3月(6)
- 2005年2月(4)
- 2005年1月(3)
- 2004年12月(1)
- 2004年11月(2)
- 2004年10月(3)
- 2004年9月(3)
- 2004年8月(2)
- 2004年7月(2)
- 2004年6月(3)
- 2004年5月(3)
- 2004年4月(4)
- 2004年3月(10)
- 2004年2月(1)
- 2004年1月(4)
- 2003年11月(3)
- 2003年10月(2)
- 2003年9月(3)
- 2003年8月(16)
- 2003年7月(1)
- 2003年6月(5)
- 2003年5月(3)
- 2003年4月(4)
- 2003年3月(8)
- 2003年2月(4)
- 2003年1月(3)
- 2002年11月(3)
- 2002年10月(2)
- 2002年9月(3)
- 2002年8月(2)
- 2002年7月(3)
- 2002年6月(5)
- 2002年5月(5)
- 2002年4月(4)
- 2002年3月(6)
- 2002年2月(6)
- 2002年1月(6)
- 2001年12月(4)
- 2001年11月(2)
- 2001年10月(4)
- 2001年9月(3)
- 2001年8月(2)
- 2001年7月(5)
- 2001年6月(5)
- 2001年5月(3)
- 2001年4月(4)
- 2001年3月(14)
- 2001年2月(3)
- 2001年1月(2)
- 2000年12月(2)
- 2000年11月(2)
- 2000年10月(4)
- 2000年9月(3)
- 2000年8月(3)
- 2000年7月(6)
- 2000年6月(3)
- 2000年5月(3)
- 2000年4月(3)
- 2000年3月(5)
- 2000年2月(4)
- 2000年1月(5)
- 1999年12月(4)
- 1999年11月(3)
- 1999年10月(2)
- 1999年9月(3)
- 1999年8月(1)
- 1999年7月(3)
- 1999年6月(3)
- 1999年5月(6)
- 1999年4月(4)
- 1999年3月(5)
- 1999年1月(3)
- 1997年12月(3)
- 1997年11月(2)
- 1997年10月(2)
- 1997年9月(3)
- 1997年8月(1)
- 1997年7月(2)
- 1997年6月(8)
- 1997年5月(5)
- 1997年4月(4)
- 1997年3月(4)
- 1997年2月(1)
- 1997年1月(3)
- 1991年2月(6)
- 1959年2月(11)