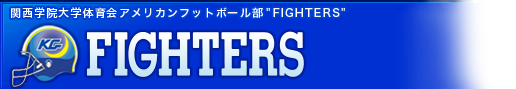米田満氏論文「アメリカン・フットボールの起源とその発展段階」
第11章 フットボールの問題点
1959/02/28
1886年以後の20年間に於てフットボールが飛躍的な発展をとげ、1906年のフォワード・パスの採用、1912年の恒久的ルールの採択、1913年のノートルダム大学の快挙によって近代フットボールに歩を運ぶ過程はすでに述べた。サッカー、ラグビーに端を発したこのスポーツはこの時期に於て完全にアメリカ固有のものとなったし、そこに至る生々発展の跡を振り返ってみる場合、フットボールがアメリカ国民性の長短所を如実に反映しながら進んできた事実を無視することはできない。フットボールが大学競技界に於て到達した最高の地位、社会的にも揺るぎないその基盤、熱狂的なファンの支持などはいずれもフットボールの具体面に現れた好現象ということができるが、他面その底に潜む数々の弊害を見逃すことはできない。フットボールの激化がひいては激しい対抗意識を生み出し、あらゆる手段を動員してあくまで勝利を追求するアメリカ的なスポーツ観は随所に混乱を巻き起こし、現在にまで及ぶ根強い悪徳の芽は実にこの時期に蒔かれた。1929年、NCAAの要請によってカーネギー財団が刊行した“アメリカのカレッジ競技(American College athletics)”と題する報告書は大学フットボールの数々の問題点をも明らかに示した。問題とされるこうした弊害を取り除くために教授会、先輩団、学生自身がそれぞれ、また相協議して数々の試みを行ったものだが、いまに至るまで根治することはできない。その第一の根拠はアメリカという国そのもの、アメリカ人という国民性それ自体の中に求められるべきであろうか。
1 アメリカに於ける大学の発達過程
弊害を生ぜしめる根本原因の一つとしてアメリカの大学の発達過程が問題となる。1865年、南北戦争の破壊と苦悩の中からアメリカの強力な国家主義が発生し、ひきつづき鉄道、通信の発達などが深遠な経済変革をもたらす根底となってアメリカの驚異的な発展を拓くこととなった。農業と工業が著しく発達し、しかもその経済分野に於ける力関係は次第に工業時代への移行を示していた。この傾向は勢い教育面にも強い反応をみせ、それ以前の智力万能主義は全く影をひそめて全国各地に技術教育のための私立大学がつぎつぎと設立されるに至った。各大学は争って学生を招致しようとし、自校を宣伝する必要に迫られて何らかの特長を持つことを求められた。そしてこの特長を多くの大学は運動競技に求め、中でも最も人気のあるフットボールがその対象となった。大学の経営者は優秀なフットボール・チームを作ることに懸命となり、次第に組織的な企業にまで進むに至って数多くの教育上の弊害を生むに至った。
2 選手の勧誘と補助制度
大学フットボールは激しい競争を伴ない、しかも各大学がひとしく優勝を望んでいるところから優秀な高校選手の獲得に狂奔した。こうして金銭その他の誘引物を提供することによって勧誘や補助の制度が生じた。勧誘を行うものは学校当局、運動部の後援会、先輩団などであり、1890年代にはその不道徳性をとくに隠弊しようとする配慮もなく、勧誘は堂々と行われていた。誘引物は入学後の生活の保障、入学試験の通知、特別な奨学金の授与などであった。金を直接やるのは比較的少なかったが、名目上の仕事に傭ったり、大学選手となれば与えられる社会的な名声、競技上の成功、大学生活の魅力といったものを強調することによって高校選手を惹きつける手段とした。
こうした勧誘、補助の制度は事あるごとに問題となり、教育的見地、アマ規定の面から鋭い批判を浴びることとなった。とくに一流大学に置いてはこの批判的態度を強く打ち出し、フットボールの粛正を叫んだが、しかしそれが一般的に迎えられる可能性はなく、地方のあまり名の通っていない大学ではその時勢からみて得をしても損をすることはないといった見解を取って、こうした不道徳性をますます巧みに隠密裡に実行に移していった。この問題は程度の差こそあれ現在に至るまで根治し得ぬものとして残されている。
3 高校への影響
優秀な高校選手を勧誘する争いが激しくなるにつれ、高校フットボール選手それ自体を始め、普ねく若い世代に強い影響を与えた。優秀な選手は大学入学以前からすでに大学選手たるの許可と生活を与えられ、一方無名選手は自己を有利に売り込むため宣伝屋を利用して各大学に通信させるような売り込み運動も行っていた。
高校の競技様式は種々の面で大学フットボールにならい、しかも高校には選手資格やスポーツマンシップの基準さえなく、教師、校長、守衛でもすべて学校チームに参加することができた。その他フットボールのシーズンだけ学校に通う選手もいた。こうして大学フットボールは直接高校選手に不正な働きかけを行ったばかりでなく、それ以上に若い世代の精神面に強い影響を与え、誤まったスポーツ観を惹起せしめるに至った。1890年代から高校に反映した大学フットボールの悪影響は1920年代に全国高校組織が確立されるまで約30年近くもつづいた。
4 商業主義
大企業化したフットボールは確固たる機構をもって運営されてゆく。学校当局は特殊なフットボール選手の立場を是認し、チーム強化のために積極的な政策を惜しまなかった。スタジアムがどんどん建ち満員の観衆がつめかけるために、儲かる企業としてフットボールの商業主義的な色彩はますます濃くなる一方であった。時代の推移によって大戦の影響、好況、不況の波などに多少左右されることはあってもフットボールの進む道が大学競技というワクを遙かに凌駕する傾向を抑えることはできなかった。
選手は職業コーチの意のままに動き、チームの活動形式に於てはプロの機構と何ら変るところはなかった。チームを強くし優秀な成績を納め得るコーチはその手腕のゆえに高額の報酬を受け、全国的に著名なコーチの中には大統領級の年俸を受ける者もあった。コーチに報酬の多寡があり、成績の不振を問われて一方的に解雇される実状など、企業としてのフットボールの一面を示すにほかならなかった。選手の具体的活動を円滑ならしめるために諸設備、用具は全て完備され、勝利という目的達成のためには莫大な費用を要した。経済的にバック・アップされたフットボール選手の生活態度は派手に流れがちであり、優秀な選手に与えられる輝かしい評判の数々は選手自身にとっても、また大学当局にとっても堕落へ陥る一つの原因ともなった。
こうした環境に於て作り上げられたフットボール・チームは単にスポーツそれ自体を楽しむためにプレーするというよりは、大きな機構の中で一つの見世物としてフットボールを行っているという印象をますます強くするばかりであった。最近のアメリカ・ニュース映画に写されるフットボール・シーンもこのことを明瞭に物語っている。少数の選手が猛烈に戦い、数万の観衆がこれを取り巻く。それに派手な応援合戦の様相などをみても完全にショー以外の何ものでもないといわざるを得ない。新聞、ラジオ、テレビが与える影響もまた甚大である。フットボールの人気を考えた場合、商業的マス・コミの世界にとって、それは恰好の好材料であり、互いに商業主義の渦中にあって密接な相関関係を持っているものということができる。大学フットボールのプロフェッショナリズム(professionalism)は競技それ自体の激化に伴なう自然の勢であったかも知れない。ややもすれば極端に流れがちなその内容はしばしば批判の的ともなったが、アメリカの国民性にはその商業主義的内容を支持してやまぬものがあるようにさえ感じられる。
大学当局はフットボール試合の利潤によって学校経営をまかない、さらにより大きな利を求めてチームに投資する。フットボール選手に金を与えることを是認する大学の論拠は単純ながら明瞭な観点に基づいている。その第一は試合をして利潤があれば働いた者に分け前を与えるのが当然であるという考えであり、第二はどんな名目にしろ選手に経済的援助を与えて実質的な雇傭関係を持つ方が賢明であるとの意図である。この論点に反対する学校ももとより多くある。そして奨励金制度の非合法化を規制する試みや申し合わせが何度か決定されたにもかかわらず、あくまで形式の域を脱せず、実質的な学生スポーツとしての理想は求むべくもない。大学フットボールはあらゆる面に於て金銭と切り離して考えることはできず、プロにつきものの賭けが常に問題とされるのもまた当然の帰結である。純真であるべき選手自身が八百長に加担するといったスキャンダルは年々その跡を断たない。
5 選手生活の内容
大企業の真只中に於て選手は最も重要な商品である。選手となるそもそもの始めから密接な経済関連に於てチームとつながる大学選手は一躍して自分のほとんど知らない基金から支出される費用で生活するという全く未知の生活水準に飛び上がることになる。彼らは大学内でも特別な存在として認められ、その生活のすべてはフットボール技の上達に向けねばならない。学生として第一義であるべき学問的探求はほとんど無視され、全時間を選手生活のために提供する。彼らはコーチの命ずるままにフォームとスタイルを改良し、策戦の綜合を完璧に実行に移すため継続的なトレーニングと厳しい訓練に服さねばならないし、相手を目の前にして決断と勇気を発揮できることを証拠立てねばならない。このため“肩幅が廣く頭蓋骨は雀のような”と皮肉な形容詞を与えられるフットボール選手が出現する。その精神生活は堕落に陥りがちであり、練習の激しさが健康をそこね、試合の激烈さが数数の障害を生む点も等閑視されず、個人的なフットボール選手それ自体にも考慮すべき多くのものが含まれている。
6 卒業生の影響
大学競技に卒業生が影響力を持つようになったのは競技それ自身の急激な発達と密接に関係する。とくに大学フットボールに対する卒業生の関心は1890年代以降の飛躍的発展期に於て著るしいものがあった。フットボールの拡大に伴ない必要経費が途方もなく増大し、やむなく特別の財政援助を卒業生に求めるということが始まった。そして卒業生はその返礼として競技自体を支配し、また次第に学校行政にすら関与する傾向をも示した。こうした卒業生の態度は感情的には愛校心に多く基づくものであり、一面社会的名声、青年層に対する奉仕の精神といった基点に立つものもあったが、経済援助によって競技支配に発言力を持つという相互関係は最初は当然の取引だとみなされていた。
19世紀末年には大多数の教授会の競技に対する態度は放任主義的なものであり、時に競技支配を考えることがあってもその結果は取るに足らぬものであった。このため卒業生のうち、この問題に積極的な関心を抱いている者がほとんど労せずして競技の支配権を得た。そしてあくまで勝利を求めてやまぬ傾向が強くなるにつれ、卒業生自身、学校当局の意向を無視してチーム強化のための高校生獲得に積極的に乗り出すといった動きが濃くなっていった。こうした卒業生の在り方はやがて学生スポーツの立場から次第に批判の的となってきた。
7 放浪選手、偽名選手
アメリカの大学では初期のころからヨーロッパ流の大学組織をそのまま採用し、ある特別な学生がある一つの科目に登録することによってその大学で堂々と資格を得ることができた。ヨーロッパに於ては純粋な学問的探求のための方策とされたこのシステムは、逆にアメリカの競技熱に利用される形となった。1890年代から1905年ごろにかけて放浪選手並びにその同類たる偽名選手が大ていのフットボール・チームに姿を現したのはこうした大学組織に便乗したものであった。そして経済的に恵まれた有力大学は小さな大学の優秀選手を引き抜くために毎年勧誘運動を行うのを普通の慣例とした。選手の引き抜きは勿論金銭と直接のつながりをもち、優秀な選手のトレードはファンの大きな関心事ともなった。この問題は1912年、ビッグ・テン協議会が初めて選手資格を厳正にする規定を取り上げたことから漸く改革の道が開かれ、その存在をなくすることに成功した。選手資格規定の中には選手期間は4年に限るとの制限、最低の学科履修を必要とする規定、一年間学校に留まるという意思の表明、転学した場合には一年間在学したのちに選手たるの資格を得るという規定などが含まれていた。
8 NCAA
以上の種々なる問題点を解決するために中心的な機関となったのは全米大学競技協会(NCAA)である。NCAAは1905年、フットボールが存続か廃止かの二者択一を迫られる最大の危機に直面した時に設立されたアメリカ大学対抗競技協会が5年後に改称されたものである。NCAAは最初から法的、執行的統制力を持たず、単に一教育団体として活動したに過ぎず、大学競技の運営は個々の大学当局の手にあったのである。そしてNCAAでは西部の大学競技協会に類似した最小限の選手資格規定を採択したが強制的方法は取らなかった。しかし時の経過とともにNCAAの存在は次第に強大なものとなり、事実上アメリカ大学競技を支配するほどの力を持つに至っている。
NCAAがアメリカの大学競技、とくにフットボールに及ぼした影響を分析するとつぎの5項目が取り上げられる。
(1) 教授会による統制
19世紀末に見られた競技統制の方法には三種類の型が識別された。その第一のものはハーバード大学に於てみられた高度に中央集権化した型で、その中に教授会、卒業生、学生の三者が協力して三部門に別れたものであった。第二のものは西部と南部で多くみられた二元計画の型であり、教授会と学生が義務を分担するものであった。第三に東部の古い大学、エール、プリンストンなどでみられたものは競技統制のすべてを学生の手でやり、時に卒業生の影響を受けることはあっても教授会の干渉がほとんど行われないというものであった。
こうした三者三様の方式をもって進んできた大学競技に対しNCAAは教授会による統制を擁護し、このことは学生および卒業生による統制から切り替えさせる要因となった。教授会自身も大学は学問の場であるべきという信念から散発的ではあっても絶えずこの問題に対する関心は伸展されつあったし、体育教師の地位の向上、心身両面の教育といった観点から競技統制に真剣な眼を向けるようになっていった。
(2)協議会の発達
NCAAの設立の年、1910年には38大学が加盟したが、NCAAは加盟校間に新しい協議会を結成することをつねに奨励した。1906年から1915年までに29の協議会が結成され、とくに中西部で盛であった。これらの協議会は加盟大学のすべての競技を規制するものであり、中西部、極西部、南部では順当な発達をとげたが、東部では競技ごとの伝統的な協会を固守する態度は依然消えやらなかった。
(3)シーズン中だけのコーチの排除
1892年、新設のシカゴ大学では正規の体育助教授としてエール大学を出たスタッグを迎え、1901年には教授の地位に昇らせた。それまでのコーチといえば学校とのつながりはなく、単にシーズン中だけ技術的な指導を行うのがほとんどであったが、このシカゴ大学の英断は大いに他を啓蒙するのに役立った。そして1910年NCAAは常勤教職員として専任のコーチを置くことを奨励する決議を行った。
(4) ルール委員会の設置
NCAA発足以来の重要な仕事の一つは各種スポーツのルール委員会の設立であった。この仕事はアメリカ競技協会、YMCA、州高校競技協会全国連合、カナダ体育協会の協力のもとで行われた。大学スポーツのルール統一は1921年の陸上競技に始まり、NCAA主催の各種スポーツの全米選手権大会計画の樹立に影響を及ぼした。フットボールはその内容からいってトーナメント試合の設立は不可能であり、その面に関しては独自の立場を取らざるを得なかったが、NCAAによって統一されたルール委員会がつねに指導的立場に立って現在に至っている。
(5) 競技拡大に伴う弊害の公知
1926年、NCAAはカーネギー財団に大学競技の調査を要請した団体の一つである。1929年に刊行された“アメリカの大学競技”と題するこの報告書は選手の勧誘やプロフェッショナリズムの容易ならざる実状を暴露した。その内容は上記の諸点に及んでいるが、このことは競技界、とくに大学フットボールの悪弊を公衆に知らせるのに大いに役立った。しかし実状を改めるという段になるとまだまだ道遠く、その可能性のほどさえ危ぶまれるものがあるといわねばならない。
(昭和34年2月)
Allison Danzig,The History of American Football,1956
Frank G.Menke,The Encyclopedia of Sports,1953
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,American College Athletics,1929
H.O."Fritz"Crisler,Modern Football,1949
Knute Rockne,Coaching,1925
加藤橘夫訳、ヴァン・ダーレン、ミッチェル、べネット共著「体育の世界史」昭和33年
加藤橘夫著「スポーツの社会学」昭和27年
木村松代、原田のぶ、原元子、藤井千代、伊藤みえ共訳、J.T.アダムズ著「米国史」昭和16年
山中良正著「アメリカスポーツ史」昭和35年
近藤等訳、ベルナール・ジレ著「スポーツの歴史」昭和31年
アーカイブ
- 2025年1月(5)
- 2024年12月(3)
- 2024年11月(13)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(6)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(9)
- 2024年5月(11)
- 2024年4月(6)
- 2024年3月(7)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(4)
- 2023年12月(10)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(1)
- 2023年6月(6)
- 2023年5月(6)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(4)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(6)
- 2022年12月(10)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(4)
- 2022年9月(4)
- 2022年8月(3)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(4)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(6)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(9)
- 2021年11月(5)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(4)
- 2021年8月(1)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(7)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(3)
- 2021年2月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(11)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(2)
- 2020年9月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年4月(7)
- 2020年3月(2)
- 2020年2月(9)
- 2020年1月(8)
- 2019年12月(12)
- 2019年11月(7)
- 2019年10月(4)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(2)
- 2019年7月(1)
- 2019年6月(5)
- 2019年5月(8)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(8)
- 2019年2月(5)
- 2019年1月(4)
- 2018年12月(11)
- 2018年11月(6)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(4)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(5)
- 2018年5月(5)
- 2018年4月(6)
- 2018年3月(9)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(11)
- 2017年11月(5)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(6)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(6)
- 2017年2月(4)
- 2017年1月(5)
- 2016年12月(11)
- 2016年11月(7)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(4)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年6月(11)
- 2016年5月(6)
- 2016年4月(4)
- 2016年3月(9)
- 2016年2月(4)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(5)
- 2015年11月(9)
- 2015年10月(2)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(3)
- 2015年7月(3)
- 2015年6月(7)
- 2015年5月(3)
- 2015年4月(2)
- 2015年3月(8)
- 2015年2月(6)
- 2015年1月(3)
- 2014年12月(10)
- 2014年11月(7)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(3)
- 2014年8月(4)
- 2014年7月(8)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(10)
- 2014年4月(4)
- 2014年3月(9)
- 2014年2月(6)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(10)
- 2013年11月(7)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(3)
- 2013年7月(5)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(5)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(5)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(8)
- 2012年11月(7)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(3)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(7)
- 2012年5月(4)
- 2012年4月(5)
- 2012年3月(6)
- 2012年2月(6)
- 2012年1月(2)
- 2011年12月(8)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(4)
- 2011年9月(4)
- 2011年8月(3)
- 2011年7月(3)
- 2011年6月(6)
- 2011年5月(6)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(9)
- 2011年2月(4)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(6)
- 2010年11月(14)
- 2010年10月(4)
- 2010年9月(3)
- 2010年8月(3)
- 2010年7月(3)
- 2010年6月(6)
- 2010年5月(4)
- 2010年4月(9)
- 2010年3月(7)
- 2010年2月(7)
- 2009年12月(1)
- 2009年11月(2)
- 2009年10月(2)
- 2009年9月(2)
- 2009年8月(4)
- 2009年7月(5)
- 2009年6月(8)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(7)
- 2009年3月(10)
- 2009年2月(3)
- 2009年1月(1)
- 2008年12月(1)
- 2008年11月(4)
- 2008年10月(2)
- 2008年9月(3)
- 2008年8月(2)
- 2008年7月(1)
- 2008年6月(5)
- 2008年5月(2)
- 2008年4月(4)
- 2008年3月(6)
- 2008年2月(1)
- 2008年1月(6)
- 2007年12月(2)
- 2007年11月(2)
- 2007年10月(2)
- 2007年9月(3)
- 2007年8月(4)
- 2007年7月(5)
- 2007年6月(8)
- 2007年5月(5)
- 2007年4月(9)
- 2007年3月(11)
- 2007年2月(3)
- 2007年1月(6)
- 2006年12月(3)
- 2006年11月(3)
- 2006年10月(4)
- 2006年9月(2)
- 2006年8月(7)
- 2006年7月(3)
- 2006年6月(7)
- 2006年5月(6)
- 2006年4月(6)
- 2006年3月(6)
- 2006年2月(3)
- 2006年1月(3)
- 2005年12月(1)
- 2005年11月(2)
- 2005年10月(3)
- 2005年9月(2)
- 2005年8月(8)
- 2005年7月(1)
- 2005年6月(4)
- 2005年5月(6)
- 2005年4月(6)
- 2005年3月(6)
- 2005年2月(4)
- 2005年1月(3)
- 2004年12月(1)
- 2004年11月(2)
- 2004年10月(3)
- 2004年9月(3)
- 2004年8月(2)
- 2004年7月(2)
- 2004年6月(3)
- 2004年5月(3)
- 2004年4月(4)
- 2004年3月(10)
- 2004年2月(1)
- 2004年1月(4)
- 2003年11月(3)
- 2003年10月(2)
- 2003年9月(3)
- 2003年8月(16)
- 2003年7月(1)
- 2003年6月(5)
- 2003年5月(3)
- 2003年4月(4)
- 2003年3月(8)
- 2003年2月(4)
- 2003年1月(3)
- 2002年11月(3)
- 2002年10月(2)
- 2002年9月(3)
- 2002年8月(2)
- 2002年7月(3)
- 2002年6月(5)
- 2002年5月(5)
- 2002年4月(4)
- 2002年3月(6)
- 2002年2月(6)
- 2002年1月(6)
- 2001年12月(4)
- 2001年11月(2)
- 2001年10月(4)
- 2001年9月(3)
- 2001年8月(2)
- 2001年7月(5)
- 2001年6月(5)
- 2001年5月(3)
- 2001年4月(4)
- 2001年3月(14)
- 2001年2月(3)
- 2001年1月(2)
- 2000年12月(2)
- 2000年11月(2)
- 2000年10月(4)
- 2000年9月(3)
- 2000年8月(3)
- 2000年7月(6)
- 2000年6月(3)
- 2000年5月(3)
- 2000年4月(3)
- 2000年3月(5)
- 2000年2月(4)
- 2000年1月(5)
- 1999年12月(4)
- 1999年11月(3)
- 1999年10月(2)
- 1999年9月(3)
- 1999年8月(1)
- 1999年7月(3)
- 1999年6月(3)
- 1999年5月(6)
- 1999年4月(4)
- 1999年3月(5)
- 1999年1月(3)
- 1997年12月(3)
- 1997年11月(2)
- 1997年10月(2)
- 1997年9月(3)
- 1997年8月(1)
- 1997年7月(2)
- 1997年6月(8)
- 1997年5月(5)
- 1997年4月(4)
- 1997年3月(4)
- 1997年2月(1)
- 1997年1月(3)
- 1991年2月(6)
- 1959年2月(11)