川口仁「日本アメリカンフットボール史-フットボールとその時代-」
| <<前へ | 次へ>> |
#23 科学的武士道 ―日本大学のフットボール 3
投稿日時:2008/11/13(木) 01:05
11月9日は朝から冷え込んでいた。早朝、刷くほどのかすかな霧雨が通り過ぎた。全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会の関西地区準決勝2試合が王子スタジアムで行われるので出かけた。阪急神戸線で、王子スタジアムの一駅手前、六甲で降りる。先日、古書店に頼んでおいた矢内正一著、『一隅の教育』を受け取るためである。その前にコンビニで神戸新聞を買う。古川明さん※の自伝、「わが心の自叙伝」の掲載が9日の日曜日から神戸新聞で始まったからである。来年にかけ30回に渡って連載されるという。古川さんのイニシャルは、A.F.つまりアメリカンフットボールである。終戦後のタッチフットボール伝来以来、フットボールとともに歩んでこられたので自叙伝は戦後の日本のフットボール史そのものの貴重な記録である。
※ #3 高校フットボールとNOBLE STUBBORNNESS参照
前回の小笠原秀宣さんからお聞きした話を続ける前に少し長くなるが紹介しておきたいことがある。#6「ダックのセカンド・ネームは」で登場いただいた丹生恭治さんが雑誌『タッチダウン』に1984年から1993年にかけて10年間書き続けられた「フットボール夜話―関学の話」という連載についてである。このシリーズは丹生さんが関西学院中学部1年生から大学4年生まで学院に在籍された10年間のことを同じ10年をかけられ綴られたものである。2006年のDVD『FIGHT ON, KWANSEI』制作のとき、チームのOBの人たちはよく「ファイターズのDNA」ということばを使った。「フットボール夜話―関学の話」を今回読み返してみるとこの連載はまさにDNAそのものを記したものであることを改めて認識することになった。
今回須山さんとお会いした目的のひとつは丹生さんが「関学の話」の中で、須山さんから聞き漏らされたと書かれているお話を聞くことにあった。大学卒業後丹生さんが現役の記者時代、国立競技場で須山さんにインタビューされた。その内容を「関学の話」の以下に書かれた。
#51「日大との出会い」、1990年9月号掲載、
#58「完敗」、1991年8月号掲載、
?須山さんが最初のゲームでプレーをしたかどうか?
(このゲームは1954年9月6日に行われ、25対7で関学の勝利。関学と日大が最初に出会ったゲームである)
?関学を破ったことは日大および関東の大学でどう受け止められたか?
(このゲームは1955年5月24日、6対18で関学が敗れた)
の2点が確認されていないことがらの主たるものであった。
?について
須山さんはスターターではなかったがゲームの大半、クォーターバッキングをされた。タッチダウンのプレーは須山さんのときであった。
?について
関学にとってはいささか肩透かしの感があるのだが、日大に甲子園ボウル連覇の覇者に勝ったという多少の感慨はあったにせよ、激戦の関東学生リーグ、特に王者立教を倒して優勝しなければならないため、勝利を評価している余裕がなかった、というのが実情であった。また当時の情報伝達力には限界があり日大の勝利は、それまで関東4連覇中の常勝立教には伝わらなかった。リーグ戦前の関東の新聞各紙予想は立教の5連覇を確実視していた。事実、日大はリーグ第3戦の慶応と引き分け、この時点でメディアの中には立教の5連覇を信じ、そう報じたものもあった。つまり日大はリーグ戦中盤になっても慶応に次ぐダークホースの位置にあった。しかしこのあと大方の予想に反し、リーグ第4戦で立教を破る。最終ゲームの法政戦を残してはいたが、法政の戦力からみて日大の勝利確実という見通しが立って始めて日大優勝の可能性濃しという記事が書かれた。
須山さんは日大一高のフットボール部のご出身である。1952年から監督になられた竹本君三さんが日本大学の系列高校にフットボール部を創ることを考えられ、最初に創部されたのが日大一高であった。指導に来校したのはのちに日大の監督になる大学1年生の篠竹幹夫さん※だった。日大一高においてタッチフットボールは後発の部であった。そのためスペースがなくコンクリート張りの場所で練習しなければならず、満足なタックル練習もできない状態であった。結果として試合はずっと無得点で敗れた。その中から須山さんはライスボウルの高校関東選抜に選ばれているのでいかに抜きん出たプレーヤーであったか想像は容易である。ぬかるんだグランドでもバランスを崩さない足腰の強さは定評だった。かつてプロ野球の西鉄ライオンズに怪童と呼ばれた中西太という巨躯(きょく)のスラッガーがいた。中西は腕っ節も足腰も強く雨でゆるんだ軟弱なグランドでも沈むことなく楽々と走塁できた。須山さんの話をOBの方からうかがったおり中西太のことを連想した。おそらく生来の素質に加え代々お祭りの御輿をかついでこられたことでさらに強化されたのであろう。
※ #4 長浜 滋賀県のフットボール その1 参照
小笠原さんの話によれば、日大はかなり早くから練習や試合中に水を補給しいたことがのちに分かったそうである。日大のゲーム終盤になっても衰えないフィットネスはこうしたことによっても支えられていた。以下カッコ内は「関学の話」、#51「日大との出会い」からの引用。
「昭和29年(1954年)9月6日※――。関学が日大と初めて出会ったのは、この日である。・・・(中略)・・・ さて、その次の日。西宮球技場に日大を迎えた私たちは、予想もしない大苦戦を強いられた。秋のシーズン開幕第1戦ということで、張り切ってはいたのだが、相手に対する認識がいささか欠落していた。それに合宿の疲れが抜け切っていなかったし、真夏同然の猛暑もあって疲労困憊のゲームだったことが、昨日のことのように思い出される。暑さとか合宿明けという点では、日大も同じ条件だった。それだけに肌で感じた相手のタフネスさ加減には、心底不気味さを覚えたことも白状しておく」
※東西学生リーグとも当時は早くて9月末ないしは10月になってリーグ戦が始まったので、こうした9月上旬のプレ・シーズン・ゲームを組むことができた。
小笠原さんは1965年(昭和40年)のご卒業である。この頃でもまだ日本のスポーツ界では水を飲むことはタブー視されていた。コンディショニングのため、あるいは安全確保のために水を補給するということが一般化するのにはまだ数年を要した。1970年前後にゲータレードという商品名に代表されるアメリカの機能性飲料が紹介されようやく知識が広がり始めた。小笠原さんによれば甲子園ボウルで対戦する日大は後半になっても動きが落ちず、最終局面になって突き放されたという。
このゲームのとき日大2年生で、のちにキャプテンを務められた笹田英次さんに日大がいつから水の補給をされ始めたかをお聞きした。笹田さんのお答えは1954年(昭和29年)、つまりこのゲームの年からである。監督であった竹本君三さんは日比谷のアメリカ文化センター※に通い“Athletic Journal”などを研究され、最新のフットボール情報を得ておられた。昭和20年代、すでに水分を補給することの有用性を知り、実行されたと考えられる。竹本監督はアンバランスTというフォーメーションを考案されるなど創意工夫に富んだ方であった。
※GHQ(連合軍最高司令官総司令部)のCIE(民間情報教育局)は日本全国に23のCIE図書館を設置した。主要都道府県の中央図書館を接収し、アメリカ文化の浸透を計るための政策を実施した。1952年に米国防省に移管され13のアメリカ文化センターとなった。そののち1972年にアメリカン・センターの名で再編成され、札幌、東京、名古屋、京都、大阪、福岡の6ヶ所にしぼり込まれた。アメリカの雑誌、本などが豊富に備えられており一般にも公開された。したがって長くアメリカ情報の窓口として利用された。筆者も学生時代に利用したことがあるが現在はどうであろうか。
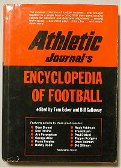
写真は“Athletic Journal”のフットボールに関する記事を集めた本
※ #3 高校フットボールとNOBLE STUBBORNNESS参照
前回の小笠原秀宣さんからお聞きした話を続ける前に少し長くなるが紹介しておきたいことがある。#6「ダックのセカンド・ネームは」で登場いただいた丹生恭治さんが雑誌『タッチダウン』に1984年から1993年にかけて10年間書き続けられた「フットボール夜話―関学の話」という連載についてである。このシリーズは丹生さんが関西学院中学部1年生から大学4年生まで学院に在籍された10年間のことを同じ10年をかけられ綴られたものである。2006年のDVD『FIGHT ON, KWANSEI』制作のとき、チームのOBの人たちはよく「ファイターズのDNA」ということばを使った。「フットボール夜話―関学の話」を今回読み返してみるとこの連載はまさにDNAそのものを記したものであることを改めて認識することになった。
今回須山さんとお会いした目的のひとつは丹生さんが「関学の話」の中で、須山さんから聞き漏らされたと書かれているお話を聞くことにあった。大学卒業後丹生さんが現役の記者時代、国立競技場で須山さんにインタビューされた。その内容を「関学の話」の以下に書かれた。
#51「日大との出会い」、1990年9月号掲載、
#58「完敗」、1991年8月号掲載、
?須山さんが最初のゲームでプレーをしたかどうか?
(このゲームは1954年9月6日に行われ、25対7で関学の勝利。関学と日大が最初に出会ったゲームである)
?関学を破ったことは日大および関東の大学でどう受け止められたか?
(このゲームは1955年5月24日、6対18で関学が敗れた)
の2点が確認されていないことがらの主たるものであった。
?について
須山さんはスターターではなかったがゲームの大半、クォーターバッキングをされた。タッチダウンのプレーは須山さんのときであった。
?について
関学にとってはいささか肩透かしの感があるのだが、日大に甲子園ボウル連覇の覇者に勝ったという多少の感慨はあったにせよ、激戦の関東学生リーグ、特に王者立教を倒して優勝しなければならないため、勝利を評価している余裕がなかった、というのが実情であった。また当時の情報伝達力には限界があり日大の勝利は、それまで関東4連覇中の常勝立教には伝わらなかった。リーグ戦前の関東の新聞各紙予想は立教の5連覇を確実視していた。事実、日大はリーグ第3戦の慶応と引き分け、この時点でメディアの中には立教の5連覇を信じ、そう報じたものもあった。つまり日大はリーグ戦中盤になっても慶応に次ぐダークホースの位置にあった。しかしこのあと大方の予想に反し、リーグ第4戦で立教を破る。最終ゲームの法政戦を残してはいたが、法政の戦力からみて日大の勝利確実という見通しが立って始めて日大優勝の可能性濃しという記事が書かれた。
須山さんは日大一高のフットボール部のご出身である。1952年から監督になられた竹本君三さんが日本大学の系列高校にフットボール部を創ることを考えられ、最初に創部されたのが日大一高であった。指導に来校したのはのちに日大の監督になる大学1年生の篠竹幹夫さん※だった。日大一高においてタッチフットボールは後発の部であった。そのためスペースがなくコンクリート張りの場所で練習しなければならず、満足なタックル練習もできない状態であった。結果として試合はずっと無得点で敗れた。その中から須山さんはライスボウルの高校関東選抜に選ばれているのでいかに抜きん出たプレーヤーであったか想像は容易である。ぬかるんだグランドでもバランスを崩さない足腰の強さは定評だった。かつてプロ野球の西鉄ライオンズに怪童と呼ばれた中西太という巨躯(きょく)のスラッガーがいた。中西は腕っ節も足腰も強く雨でゆるんだ軟弱なグランドでも沈むことなく楽々と走塁できた。須山さんの話をOBの方からうかがったおり中西太のことを連想した。おそらく生来の素質に加え代々お祭りの御輿をかついでこられたことでさらに強化されたのであろう。
※ #4 長浜 滋賀県のフットボール その1 参照
小笠原さんの話によれば、日大はかなり早くから練習や試合中に水を補給しいたことがのちに分かったそうである。日大のゲーム終盤になっても衰えないフィットネスはこうしたことによっても支えられていた。以下カッコ内は「関学の話」、#51「日大との出会い」からの引用。
「昭和29年(1954年)9月6日※――。関学が日大と初めて出会ったのは、この日である。・・・(中略)・・・ さて、その次の日。西宮球技場に日大を迎えた私たちは、予想もしない大苦戦を強いられた。秋のシーズン開幕第1戦ということで、張り切ってはいたのだが、相手に対する認識がいささか欠落していた。それに合宿の疲れが抜け切っていなかったし、真夏同然の猛暑もあって疲労困憊のゲームだったことが、昨日のことのように思い出される。暑さとか合宿明けという点では、日大も同じ条件だった。それだけに肌で感じた相手のタフネスさ加減には、心底不気味さを覚えたことも白状しておく」
※東西学生リーグとも当時は早くて9月末ないしは10月になってリーグ戦が始まったので、こうした9月上旬のプレ・シーズン・ゲームを組むことができた。
小笠原さんは1965年(昭和40年)のご卒業である。この頃でもまだ日本のスポーツ界では水を飲むことはタブー視されていた。コンディショニングのため、あるいは安全確保のために水を補給するということが一般化するのにはまだ数年を要した。1970年前後にゲータレードという商品名に代表されるアメリカの機能性飲料が紹介されようやく知識が広がり始めた。小笠原さんによれば甲子園ボウルで対戦する日大は後半になっても動きが落ちず、最終局面になって突き放されたという。
このゲームのとき日大2年生で、のちにキャプテンを務められた笹田英次さんに日大がいつから水の補給をされ始めたかをお聞きした。笹田さんのお答えは1954年(昭和29年)、つまりこのゲームの年からである。監督であった竹本君三さんは日比谷のアメリカ文化センター※に通い“Athletic Journal”などを研究され、最新のフットボール情報を得ておられた。昭和20年代、すでに水分を補給することの有用性を知り、実行されたと考えられる。竹本監督はアンバランスTというフォーメーションを考案されるなど創意工夫に富んだ方であった。
※GHQ(連合軍最高司令官総司令部)のCIE(民間情報教育局)は日本全国に23のCIE図書館を設置した。主要都道府県の中央図書館を接収し、アメリカ文化の浸透を計るための政策を実施した。1952年に米国防省に移管され13のアメリカ文化センターとなった。そののち1972年にアメリカン・センターの名で再編成され、札幌、東京、名古屋、京都、大阪、福岡の6ヶ所にしぼり込まれた。アメリカの雑誌、本などが豊富に備えられており一般にも公開された。したがって長くアメリカ情報の窓口として利用された。筆者も学生時代に利用したことがあるが現在はどうであろうか。
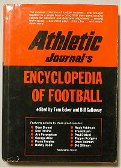
写真は“Athletic Journal”のフットボールに関する記事を集めた本
#22 科学的武士道 ―日本大学のフットボール 2
投稿日時:2008/11/02(日) 22:10
11月1日はフットボール日和だった。西京極陸上競技場へ関学のゲームを見に行った。1時頃着くとバック・スタンドは、ほぼいっぱいになっていた。最近関学サイドのスタンドは満杯状態が多い。例えば王子スタジアムのバック・スタンドでは収容し切れなくなっている。いつも一緒に観戦させていただく方々がざっと見渡しても見つからなかった。少し上段の席を捜したが空いていないように見えた。しばらくして席に荷物を置かれていた方が空けてくださった。その方にお話を聞くと第一試合から来ておられたとのこと。今日は朝から所用があって家を出るのが遅くなった。
第一試合が終って少ししたところで携帯に「フットボールの神様」から電話が入った。大藤 努さんだった。大藤さんは前回書いた1955年(昭和30年)、第10回甲子園ボウルの関学のエース・ランナーだった方である。ファイターズの65周年DVD製作の時、米田豊さん※からのご紹介でたいへんお世話になった。DVDに出てくるフォーメーションは大藤さんが私の取材ノートに書かれたものをそのまま掲載したものである。
※ #5 米田 豊さんインタビュー参照
すぐに電話を替わられた。出てこられたのは木谷 直行さんだった。木谷さんは大藤さんと同級生で4年生のときはキャプテン、第10回大会のときも実質的なチーム・リーダーであった方である。学業では一番、卒業生総代、スポーツにおいては甲子園ボウル3勝1分け、1分けは両校優勝なので都合4回優勝され、文武両道の人として半ば伝説化した方である。昨日、取材をさせていただいた。超一流の大企業に就職され要職に就かれながら、ファイターズの監督もされた。ラグビーにおける宿沢広朗氏と似たキャリアである。監督のときも現役時代と同様に甲子園では不敗であり、強運の持ち主である。また、チームマネージメントにおいてもすぐれた手腕を発揮された。ファイターズが個人商店ではなく企業のように運営されているのも木谷さんをはじめとする方々のリベラルな考え方によっている。
木谷さんとは昨日お会いし、インタビューをさせていただいた。お話は理路整然としていて、こちらの意図を理解された上で話を展開されるので、ほとんどの時間、記録に専念できた。脱帽である。昨日お願いした資料のコピーをもってきたのでこちらへ来ませんか、というお誘いであった。木谷さん、大藤さんが座っておられるまわりは大先輩ばかりである。大藤さんの慫慂(しょうよう)でお二人の間に座らせていただくことになった。ゲームの経過とともにお二人が一言、二言、ぽつんと言われることがすべてポイントをついている。関西学院の中学部からフットボールをされ、その後も長く見守ってこられたので当然といえば当然なのだが、根底に非情に暖かいものがあってこんなに気分よくフットボールを観戦したのは初めてであった。
大藤さんは現役当時、常にラッキー・ボーイと呼ばれた方である。鋭い勘をお持ちなのと観察眼が優れておられるので、人より何歩も先のことが見えているようである。その走りっぷりは現役時代、カニ走りと呼ばれ真横にカットが切れたらしい。この話は木谷さんからお聞きした。過去にそのような走り方ができたのは私の記憶の中ではただひとりである。現在、ファイターズのコーチ、小野宏さんである。西宮球技場でサイドラインから反対のサイドラインまで真横に瞬間移動したように見えたプレーが鮮烈な記憶として残っている。実際にはそうしたことは物理的にはないのだが、その魔法のようなシーンは今も目に焼き付いている。
第3Q、7分を過ぎたあたりで、相手チームのパントになった。大藤さんが「パント・ブロック」といわれた。次の瞬間それが本当に起こった。第4Qが始まってすぐの頃、「QB、つぶせ」と大藤さんが叫ばれた。相手チームのQBが軽自動車がダンプカーと正面衝突したかのように関学のディフェンス・ラインに大きく吹き飛ばされ、その手から弾けるようにボールがバック・フィールドに転がり出た。ボールを追っているのは白いジャージの大きなラインである。#51が器用にボールを拾い上げると40ヤード、5秒5くらいのスピードでゴール・ラインに向かって走り出した。まわりを白いジャージがガードし相手の追跡を阻んでいる。そのまま60ヤードあまりを追いつかれることなくTD。先ほど関西学生アメリカンフットボール連盟のホームページで記録を確かめたら64ヤードだった。川島君にとっては初めてのTDではないだろうか。ディフェンス・ラインがタッチ・ダウンした距離としては新記録かも知れない。
帰途、米田さんにお渡しするものがあって、ファイターズのグッズを売っているテントの前で待っていた。勝利は販促に最大の効果があるようで、テントの間口がすぐに人でいっぱいになりグッズが次々に売れた。
米田さんとはそこでお別れしたが、帰路もフットボールの神様と同行させていただくことになった。今度はフットボールの神様が以前から顔なじみの小笠原秀宣さんになられた。西京極から十三駅まで40分ほどかかるのだが話がはずみ瞬く間に時間がすぎた。その間、小笠原さんから日本大学の科学性についてお聞きすることになるとは家を出るときまったく予想もしなかったことである。このことは次回に。

木谷さんが高校生時代、勉強された“Functional Football”という英語の本。滋賀県立旧制彦根中学(現在、彦根東高校)のタッチフットボール部の方もこの本で学ばれた。
第一試合が終って少ししたところで携帯に「フットボールの神様」から電話が入った。大藤 努さんだった。大藤さんは前回書いた1955年(昭和30年)、第10回甲子園ボウルの関学のエース・ランナーだった方である。ファイターズの65周年DVD製作の時、米田豊さん※からのご紹介でたいへんお世話になった。DVDに出てくるフォーメーションは大藤さんが私の取材ノートに書かれたものをそのまま掲載したものである。
※ #5 米田 豊さんインタビュー参照
すぐに電話を替わられた。出てこられたのは木谷 直行さんだった。木谷さんは大藤さんと同級生で4年生のときはキャプテン、第10回大会のときも実質的なチーム・リーダーであった方である。学業では一番、卒業生総代、スポーツにおいては甲子園ボウル3勝1分け、1分けは両校優勝なので都合4回優勝され、文武両道の人として半ば伝説化した方である。昨日、取材をさせていただいた。超一流の大企業に就職され要職に就かれながら、ファイターズの監督もされた。ラグビーにおける宿沢広朗氏と似たキャリアである。監督のときも現役時代と同様に甲子園では不敗であり、強運の持ち主である。また、チームマネージメントにおいてもすぐれた手腕を発揮された。ファイターズが個人商店ではなく企業のように運営されているのも木谷さんをはじめとする方々のリベラルな考え方によっている。
木谷さんとは昨日お会いし、インタビューをさせていただいた。お話は理路整然としていて、こちらの意図を理解された上で話を展開されるので、ほとんどの時間、記録に専念できた。脱帽である。昨日お願いした資料のコピーをもってきたのでこちらへ来ませんか、というお誘いであった。木谷さん、大藤さんが座っておられるまわりは大先輩ばかりである。大藤さんの慫慂(しょうよう)でお二人の間に座らせていただくことになった。ゲームの経過とともにお二人が一言、二言、ぽつんと言われることがすべてポイントをついている。関西学院の中学部からフットボールをされ、その後も長く見守ってこられたので当然といえば当然なのだが、根底に非情に暖かいものがあってこんなに気分よくフットボールを観戦したのは初めてであった。
大藤さんは現役当時、常にラッキー・ボーイと呼ばれた方である。鋭い勘をお持ちなのと観察眼が優れておられるので、人より何歩も先のことが見えているようである。その走りっぷりは現役時代、カニ走りと呼ばれ真横にカットが切れたらしい。この話は木谷さんからお聞きした。過去にそのような走り方ができたのは私の記憶の中ではただひとりである。現在、ファイターズのコーチ、小野宏さんである。西宮球技場でサイドラインから反対のサイドラインまで真横に瞬間移動したように見えたプレーが鮮烈な記憶として残っている。実際にはそうしたことは物理的にはないのだが、その魔法のようなシーンは今も目に焼き付いている。
第3Q、7分を過ぎたあたりで、相手チームのパントになった。大藤さんが「パント・ブロック」といわれた。次の瞬間それが本当に起こった。第4Qが始まってすぐの頃、「QB、つぶせ」と大藤さんが叫ばれた。相手チームのQBが軽自動車がダンプカーと正面衝突したかのように関学のディフェンス・ラインに大きく吹き飛ばされ、その手から弾けるようにボールがバック・フィールドに転がり出た。ボールを追っているのは白いジャージの大きなラインである。#51が器用にボールを拾い上げると40ヤード、5秒5くらいのスピードでゴール・ラインに向かって走り出した。まわりを白いジャージがガードし相手の追跡を阻んでいる。そのまま60ヤードあまりを追いつかれることなくTD。先ほど関西学生アメリカンフットボール連盟のホームページで記録を確かめたら64ヤードだった。川島君にとっては初めてのTDではないだろうか。ディフェンス・ラインがタッチ・ダウンした距離としては新記録かも知れない。
帰途、米田さんにお渡しするものがあって、ファイターズのグッズを売っているテントの前で待っていた。勝利は販促に最大の効果があるようで、テントの間口がすぐに人でいっぱいになりグッズが次々に売れた。
米田さんとはそこでお別れしたが、帰路もフットボールの神様と同行させていただくことになった。今度はフットボールの神様が以前から顔なじみの小笠原秀宣さんになられた。西京極から十三駅まで40分ほどかかるのだが話がはずみ瞬く間に時間がすぎた。その間、小笠原さんから日本大学の科学性についてお聞きすることになるとは家を出るときまったく予想もしなかったことである。このことは次回に。

木谷さんが高校生時代、勉強された“Functional Football”という英語の本。滋賀県立旧制彦根中学(現在、彦根東高校)のタッチフットボール部の方もこの本で学ばれた。
| «前へ | 次へ» |



