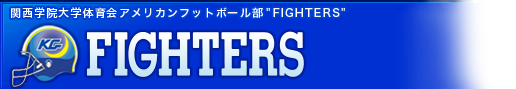石井晃のKGファイターズコラム「スタンドから」
| <<前へ | 次へ>> |
(33)課外活動と興行
投稿日時:2019/01/05(土) 22:26
くそったれ!
ライスボウルが終了したとき、思わずこんな言葉が口から飛び出した。あまりにも品のない言葉であり、それを文章にするなんてもってのほかだ。
けれども、試合が終わって3日目の今朝、なんとかパソコンに向かって今季の最終回となるコラムを書こうとしても、この汚い言葉が頭の中を走り回っている。とても原稿を書く気分ではない。いっそ、前回のコラムのままで、光藤ファイターズの今季を締めくくってしまおうかとも考えた。
けれども、いかに苦しくても、戦いを最期まで見届けるのが「従軍記者」の務めである。顔を洗い、口をすすいで、あらためてパソコンと向き合っている。
試合そのものについては、主催者の一員でもある朝日新聞がしっかり書いてくれている。その筆者のリーダー格がファイターズOBの榊原一生君(2001年度卒)と大西史恭君(2007年度卒)。ともにファイターズの内部情報にも通じており、専門記者ならではの冷静、公平な記事を仕上げている。
だから、僕はあえて試合の進行状況とは離れ、ライスボウルの位置付けと大学スポーツが目指す方向の2点から、僕なりの感想を綴ってみる。見苦しい言葉があるかもしれないが、ご寛恕を賜りたい。
1、ライスボウルとは
いうまでもなく、社会人王者と大学王者がフットボール日本1を決める戦いとして位置づけられている。以前は学生チームの東西対抗戦として開催されていたが、1984年以降は社会人トップと学生トップが日本1の座を競う日本選手権となった。当時は、社会人の選手層も薄く、加盟チームの力量も学生側と大差はなかった。逆に大学側には、その前の甲子園ボウルに勝つことを最終目標としているチームが多く、ライスボウルはその勝者に対するご褒美という程度の位置づけをしていたような印象がある。
少なくともファイターズにとっては、甲子園ボウルに勝つことが至上命題であり、その前に、80年代は京大に勝って甲子園ボウルに、そして90年代は京大、立命に勝って甲子園ボウルに出ること、甲子園ボウルで関東代表を倒して、名実ともに日本1となることが最大の目標とされていたように僕は理解している。だから関西リーグは盛り上がり、互いが互いを意識して切磋琢磨し、全体のレベルも上がった。京大と関学の戦いには3万人の観衆が詰めかけることも珍しくなく、甲子園ボウルで関西リーグの代表が勝っても「当たり前」というような状況が生まれた。
課外活動としてのフットボールに情熱を傾ける学生と学生が、互いに4年間という対等の時間の中で錬磨し、知恵を巡らせて戦い、純粋に勝つことに誇りを持てた時代といってもよい。
90年代に入ると、社会人チームの取り組みが本格化し、学生チームもまたライスボウルで勝つことを最終目標にするようになった。とりわけ社会人チームは、大学のスター選手を次々確保するようになり、2000年代に入ると、それがさらに加速された。専任のプロコーチを置いたり、アメリカから選手を呼び込んでチームを強化したりするチームが増え、その実力も年々アップしている。
さらにいえば、アメリカからの選手が増えるにつれて、試合そのものも「興行・イベント」としての色彩が濃くなり、チアリーダーの応援もショウアップされた。スポーツイベントだから、観客動員が重要視され、それに伴って大音響のクラウドノイズも当たり前になった。
逆に学生チームは4年間という年限があることに加え、近年はフットボール選手である前に大学生であれ、という流れが定着してきた。ファイターズのように、授業優先の練習時間を設定し、所定の単位を取得しなければ、試合には出場させないとか、練習も制限するとかのルールを決めて取り組んでいるチームもある。
「興行」である以上、強くあらねばならない。その目的を達成するために人材の補強、指導者の招請、スタッフの強化などチームマネジメントに取り組む社会人チームと、4年限りの短い時間で学生を育て、手持ちの資源だけで勝負する学生チーム。双方のフットボール哲学、目的の乖離は年々大きくなり、それに応じてチーム力の差も開き続けている。その集大成が今年のライスボウルであったといっても過言ではなかろう。
2、大学スポーツとは
では、大学スポーツも社会人と同じ方向を目指せばいいのか。日本選手権(ライスボウル)の在り方が現行通りなら、そこで勝つためには、大学側も社会人チームと同等の取り組みをしなければならない。しかし、大学生が取り組む課外活動として位置づける限り、野放図なことは許されない。
大学生活は20歳前後の4年間。その限られた時間で、学業に取り組みながら課外活動にも力を注ぐ。そこで人格を養い、忍耐力や協調性、思考力や発想力を身に付ける。「どんな男(人間)になんねん」と問い続けて自ら奮起し、明日を信じて身を処していく。
それが人間としての成長につながり、その成長を担保する仕組みが大学における課外活動であり正課外教育である。
ファイターズの活動もそうした活動の一つであり、だからこそ、学生たちはその活動に4年間集中して取り組み、涙を流し、喜びを爆発させる。仲間との絆を深め、生涯の友人に巡り会う。
それはこの1年間、光藤ファイターズが歩んできた道のりそのものである。5月、雨の中での日体大との試合で敗れたところから再スタートしたチームは、何度も奈落の底に落ちそうになりながら踏みとどまった。苦しい関大戦を残り2分からの逆襲でなんとか引き分けに持ち込んだ。2度にわたる立命との決戦も、チームが一体となって乗り切った。手の内が分からないままの甲子園ボウル、早稲田との戦いも、ファイターズならではの戦術を駆使して乗り切った。コーチ陣を含めたチームの総合力でつかんだ勝利といってもよいだろう。
そうしてたどり着いたライスボウル。試合は大差がついたが、学生代表の戦いとして堂々と胸を張れる試合だったと僕は思っている。大差の中でも必死に走り、パスを投げ、捕り続けたQB、RB、WR陣。それを支えたOLの面々。三笠を中心とする守備陣も頑張った。立ち上がりから強力なタックルで相手エースを止め続けたDLとLB。とりわけ2年生の海崎、繁治の懸命のプレーには涙が出そうだった。DBの横澤、西原、木村、畑中らも終始、相手のレシーバーに食らいついた。
その結果としての52-17。興行ではなく、大学生が課外活動として取り組んだフットボールの試合として、胸が張れる結果だと僕は思っている。
ありがとう。光藤ファイターズ。シーズン半ばから急激に成長し、ライスボウルで懸命に戦って散った諸君の姿を僕は忘れない。
ライスボウルが終了したとき、思わずこんな言葉が口から飛び出した。あまりにも品のない言葉であり、それを文章にするなんてもってのほかだ。
けれども、試合が終わって3日目の今朝、なんとかパソコンに向かって今季の最終回となるコラムを書こうとしても、この汚い言葉が頭の中を走り回っている。とても原稿を書く気分ではない。いっそ、前回のコラムのままで、光藤ファイターズの今季を締めくくってしまおうかとも考えた。
けれども、いかに苦しくても、戦いを最期まで見届けるのが「従軍記者」の務めである。顔を洗い、口をすすいで、あらためてパソコンと向き合っている。
試合そのものについては、主催者の一員でもある朝日新聞がしっかり書いてくれている。その筆者のリーダー格がファイターズOBの榊原一生君(2001年度卒)と大西史恭君(2007年度卒)。ともにファイターズの内部情報にも通じており、専門記者ならではの冷静、公平な記事を仕上げている。
だから、僕はあえて試合の進行状況とは離れ、ライスボウルの位置付けと大学スポーツが目指す方向の2点から、僕なりの感想を綴ってみる。見苦しい言葉があるかもしれないが、ご寛恕を賜りたい。
1、ライスボウルとは
いうまでもなく、社会人王者と大学王者がフットボール日本1を決める戦いとして位置づけられている。以前は学生チームの東西対抗戦として開催されていたが、1984年以降は社会人トップと学生トップが日本1の座を競う日本選手権となった。当時は、社会人の選手層も薄く、加盟チームの力量も学生側と大差はなかった。逆に大学側には、その前の甲子園ボウルに勝つことを最終目標としているチームが多く、ライスボウルはその勝者に対するご褒美という程度の位置づけをしていたような印象がある。
少なくともファイターズにとっては、甲子園ボウルに勝つことが至上命題であり、その前に、80年代は京大に勝って甲子園ボウルに、そして90年代は京大、立命に勝って甲子園ボウルに出ること、甲子園ボウルで関東代表を倒して、名実ともに日本1となることが最大の目標とされていたように僕は理解している。だから関西リーグは盛り上がり、互いが互いを意識して切磋琢磨し、全体のレベルも上がった。京大と関学の戦いには3万人の観衆が詰めかけることも珍しくなく、甲子園ボウルで関西リーグの代表が勝っても「当たり前」というような状況が生まれた。
課外活動としてのフットボールに情熱を傾ける学生と学生が、互いに4年間という対等の時間の中で錬磨し、知恵を巡らせて戦い、純粋に勝つことに誇りを持てた時代といってもよい。
90年代に入ると、社会人チームの取り組みが本格化し、学生チームもまたライスボウルで勝つことを最終目標にするようになった。とりわけ社会人チームは、大学のスター選手を次々確保するようになり、2000年代に入ると、それがさらに加速された。専任のプロコーチを置いたり、アメリカから選手を呼び込んでチームを強化したりするチームが増え、その実力も年々アップしている。
さらにいえば、アメリカからの選手が増えるにつれて、試合そのものも「興行・イベント」としての色彩が濃くなり、チアリーダーの応援もショウアップされた。スポーツイベントだから、観客動員が重要視され、それに伴って大音響のクラウドノイズも当たり前になった。
逆に学生チームは4年間という年限があることに加え、近年はフットボール選手である前に大学生であれ、という流れが定着してきた。ファイターズのように、授業優先の練習時間を設定し、所定の単位を取得しなければ、試合には出場させないとか、練習も制限するとかのルールを決めて取り組んでいるチームもある。
「興行」である以上、強くあらねばならない。その目的を達成するために人材の補強、指導者の招請、スタッフの強化などチームマネジメントに取り組む社会人チームと、4年限りの短い時間で学生を育て、手持ちの資源だけで勝負する学生チーム。双方のフットボール哲学、目的の乖離は年々大きくなり、それに応じてチーム力の差も開き続けている。その集大成が今年のライスボウルであったといっても過言ではなかろう。
2、大学スポーツとは
では、大学スポーツも社会人と同じ方向を目指せばいいのか。日本選手権(ライスボウル)の在り方が現行通りなら、そこで勝つためには、大学側も社会人チームと同等の取り組みをしなければならない。しかし、大学生が取り組む課外活動として位置づける限り、野放図なことは許されない。
大学生活は20歳前後の4年間。その限られた時間で、学業に取り組みながら課外活動にも力を注ぐ。そこで人格を養い、忍耐力や協調性、思考力や発想力を身に付ける。「どんな男(人間)になんねん」と問い続けて自ら奮起し、明日を信じて身を処していく。
それが人間としての成長につながり、その成長を担保する仕組みが大学における課外活動であり正課外教育である。
ファイターズの活動もそうした活動の一つであり、だからこそ、学生たちはその活動に4年間集中して取り組み、涙を流し、喜びを爆発させる。仲間との絆を深め、生涯の友人に巡り会う。
それはこの1年間、光藤ファイターズが歩んできた道のりそのものである。5月、雨の中での日体大との試合で敗れたところから再スタートしたチームは、何度も奈落の底に落ちそうになりながら踏みとどまった。苦しい関大戦を残り2分からの逆襲でなんとか引き分けに持ち込んだ。2度にわたる立命との決戦も、チームが一体となって乗り切った。手の内が分からないままの甲子園ボウル、早稲田との戦いも、ファイターズならではの戦術を駆使して乗り切った。コーチ陣を含めたチームの総合力でつかんだ勝利といってもよいだろう。
そうしてたどり着いたライスボウル。試合は大差がついたが、学生代表の戦いとして堂々と胸を張れる試合だったと僕は思っている。大差の中でも必死に走り、パスを投げ、捕り続けたQB、RB、WR陣。それを支えたOLの面々。三笠を中心とする守備陣も頑張った。立ち上がりから強力なタックルで相手エースを止め続けたDLとLB。とりわけ2年生の海崎、繁治の懸命のプレーには涙が出そうだった。DBの横澤、西原、木村、畑中らも終始、相手のレシーバーに食らいついた。
その結果としての52-17。興行ではなく、大学生が課外活動として取り組んだフットボールの試合として、胸が張れる結果だと僕は思っている。
ありがとう。光藤ファイターズ。シーズン半ばから急激に成長し、ライスボウルで懸命に戦って散った諸君の姿を僕は忘れない。
(32)祈りと浪花節
投稿日時:2018/12/24(月) 21:49
「ファイターズはよく祈る」と、ファイターズの顧問であり、関西学院の宗教総主事やファイターズの副部長を務められた前島宗甫先生が神学部の「後援会便り」にお書きになっている。
こんな内容である。
? 1月末の卒業生壮行会、4月1日、新チームの練習スタート時、8月1日は秋本番の練習に向けて、そして春、秋のそれぞれの試合前、最終のライスボウルまで勝ち上がると、祈りの時間は都合20回近くなる。
? 始まりは1977年11月。後に「涙の日生球場」と語り次がれる京大との激戦の前に、チームドクターだった今は亡き杉本公允医師(塚口教会員)が自然発生的に選手たちと祈られたのがきっかけ。その後、元コーチで宗教センターの職員だった古結章司さんが渡米された際カレッジの試合で祈りが持たれていることを知り、取り入れることを進言。ビッグゲームなどで祈りが行われるようになった。
? 2003年の夏、平郡雷太君が急死した。(ファイターズの副部長だった私は)学生らの要望で記念会を行い、それ以降、試合の直前に祈るようになった。以来今日まで全試合前に行われている。私は退職した後も顧問に任じられ、祈りを担当してきた。これは部長や監督が命じたものではない。部員たちの自主性による。毎年新チームになると、主務が「今年もお願いします」と依頼に来る。
? 試合開始10分前。選手、コーチ、スタッフ全員が集まる。プレッシャーが最高にかかる瞬間である。聖書を読み、それにちなんで語り掛け、祈る。その間、約2分と決めている。選手たちのテンションの高さは半端ではない。クールダウンさせつつ、モチベーションは下げない。「腑に落ちる」言葉が求められる。
? 学生たちはどう受け止めているだろうか。「気持ちがぐっと引き締まる瞬間」(2011年、長島義明副将)、「一つになるために必要な時間」(2014年、鷺野聡主将)……。
以上のようなことを書き「ファイターズは祈りを育ててきた。学生たちが自らの思い、志を育ててきた。グラウンドでまたミーティングで思いをぶつけ合い体現してきた」「強いファイターズであると同時にファイター一人一人の人間性が問われる。関西学院という教育機関の課外教育の意味がここにある」と結ばれている。
前島先生の祈りだけではない。ファイターズでは、毎年新しいシーズンが始まる前、鳥内監督が新しく4年生になる一人一人の部員と時間を掛けて面談し「どんな男になんねん」「どんな風にチームに貢献すんねん」と問い掛けられる。ビッグゲームの試合前日には必ず4年生とホテルに泊まり込み、選手一人一人の覚悟を問われる。
小野宏ディレクターは、コーチの時代、これまたビッグゲームの前には第3フィールドの中央に選手を集め、「堂々と勝ち、堂々と負けよ」から始まるカール・ダイムの詩を読み上げ、戦いに挑む戦士の士気を鼓舞されていた。それぞれが魂の深いところに問い掛けるスピリチュアルな試みであり「やらされる」フットボールではなく、「部員自らが思い、志を育てる」手助けである。
こんな風に書いていくと、ファイターズはなんと窮屈なチームだろう、と早とちりされるかもしれない。しかし、現場でチームに寄り添っていると、決してそんなことはない。
この前の甲子園ボウル。試合終了間際のファイターズの攻撃シリーズを思い浮かべてみると、それが即座に理解されるはずだ。
残り時間約1分30秒。得点は37-20でファイターズがリード。タッチダウンを2本とっても追いつかない局面でファイターズの攻撃が始まる。相手陣45ヤードからの第一プレーはQB西野からWR阿部への34ヤードパス。ゴール前11ヤードからの攻撃ではRB富永に立て続けにボールを持たせて第4ダウン残り1ヤード。相手ゴールまで残り2ヤードという局面で足の負傷で試合に出られないRB山口がチームメートに支えられるようにしてRBのポジションに着く。
ファイターズファンが陣取ったレフト側アルプス席と外野席から万雷の拍手が送られる。立命との決戦で鮮やかな独走TDを挙げただけでなく、今季の攻撃陣を終始リードしてきた彼をどうしても甲子園のグラウンドに立たせたいというコーチとチームメートの思いを汲んだベンチの計らいだった。
試合後、グラウンドに降り、喜びで顔をくしゃくしゃにしているQB奥野やRB中村らの右腕にそれぞれマジックで「34」と書き込まれているのを見、それが山口自身の手で書き込まれたと聞いたとき、僕は思わず「よっしゃー。これがファイターズや」とコブシを握った。
近くの大村コーチに聞くと「早稲田さんに失礼かとも思ったんですけど、どうしても最後の場面ではけがで苦労したメンバーを出したかった。山口はもちろん、最後にけがをした西野にも思い切りパスを投げさせられたし、この1年以上、ずっとけがで苦しみながらパートを引っ張ってきた富永も走らせることができた。4年生最後の甲子園。努力してきたヤツが思い残すことのないようにしてやりたかった」という答えが返ってきた。
まるで浪花節の世界である。けれども、ファイターズにとっては、こうした浪花節のよう気配りは珍しいことではない。2013年、日大と戦った甲子園ボウルでは直前に大けがをした池田雄紀君を副将の鳥内将希君や主将の池永健人君らが抱きかかえるようにしてサイドラインに並ばせたし、翌年はこれまた甲子園ボウル直前にけがをしたWRの横山公則君を周囲の4年生が包み込むようにして入場門を入っていった。
共同通信の宍戸博昭さん(日大OB)が最近の自身のコラムにこんなことを書いておられる。「全盛期の日大は、篠竹監督の個人商店、ファイターズは組織で勝負する総合商社」「ゲームプラン、プレーのデザイン、コールを含めて、よくコーチングされた関学の選手は相手の弱点を見逃さないしたたかさと高い遂行力を備えていた」……。
少々褒めすぎのような気もするが、選手に高い精神性を求め、魂の根幹に触れる祈りと、人間の感情に訴え、熱き血を奮い立たせ、涙を共有する浪花節が共存し、融合するファイターズのたたずまいに接していると、なるほど、これが総合商社と呼ばれる理由かも知れないという気がしてきた。
こんな内容である。
? 1月末の卒業生壮行会、4月1日、新チームの練習スタート時、8月1日は秋本番の練習に向けて、そして春、秋のそれぞれの試合前、最終のライスボウルまで勝ち上がると、祈りの時間は都合20回近くなる。
? 始まりは1977年11月。後に「涙の日生球場」と語り次がれる京大との激戦の前に、チームドクターだった今は亡き杉本公允医師(塚口教会員)が自然発生的に選手たちと祈られたのがきっかけ。その後、元コーチで宗教センターの職員だった古結章司さんが渡米された際カレッジの試合で祈りが持たれていることを知り、取り入れることを進言。ビッグゲームなどで祈りが行われるようになった。
? 2003年の夏、平郡雷太君が急死した。(ファイターズの副部長だった私は)学生らの要望で記念会を行い、それ以降、試合の直前に祈るようになった。以来今日まで全試合前に行われている。私は退職した後も顧問に任じられ、祈りを担当してきた。これは部長や監督が命じたものではない。部員たちの自主性による。毎年新チームになると、主務が「今年もお願いします」と依頼に来る。
? 試合開始10分前。選手、コーチ、スタッフ全員が集まる。プレッシャーが最高にかかる瞬間である。聖書を読み、それにちなんで語り掛け、祈る。その間、約2分と決めている。選手たちのテンションの高さは半端ではない。クールダウンさせつつ、モチベーションは下げない。「腑に落ちる」言葉が求められる。
? 学生たちはどう受け止めているだろうか。「気持ちがぐっと引き締まる瞬間」(2011年、長島義明副将)、「一つになるために必要な時間」(2014年、鷺野聡主将)……。
以上のようなことを書き「ファイターズは祈りを育ててきた。学生たちが自らの思い、志を育ててきた。グラウンドでまたミーティングで思いをぶつけ合い体現してきた」「強いファイターズであると同時にファイター一人一人の人間性が問われる。関西学院という教育機関の課外教育の意味がここにある」と結ばれている。
前島先生の祈りだけではない。ファイターズでは、毎年新しいシーズンが始まる前、鳥内監督が新しく4年生になる一人一人の部員と時間を掛けて面談し「どんな男になんねん」「どんな風にチームに貢献すんねん」と問い掛けられる。ビッグゲームの試合前日には必ず4年生とホテルに泊まり込み、選手一人一人の覚悟を問われる。
小野宏ディレクターは、コーチの時代、これまたビッグゲームの前には第3フィールドの中央に選手を集め、「堂々と勝ち、堂々と負けよ」から始まるカール・ダイムの詩を読み上げ、戦いに挑む戦士の士気を鼓舞されていた。それぞれが魂の深いところに問い掛けるスピリチュアルな試みであり「やらされる」フットボールではなく、「部員自らが思い、志を育てる」手助けである。
こんな風に書いていくと、ファイターズはなんと窮屈なチームだろう、と早とちりされるかもしれない。しかし、現場でチームに寄り添っていると、決してそんなことはない。
この前の甲子園ボウル。試合終了間際のファイターズの攻撃シリーズを思い浮かべてみると、それが即座に理解されるはずだ。
残り時間約1分30秒。得点は37-20でファイターズがリード。タッチダウンを2本とっても追いつかない局面でファイターズの攻撃が始まる。相手陣45ヤードからの第一プレーはQB西野からWR阿部への34ヤードパス。ゴール前11ヤードからの攻撃ではRB富永に立て続けにボールを持たせて第4ダウン残り1ヤード。相手ゴールまで残り2ヤードという局面で足の負傷で試合に出られないRB山口がチームメートに支えられるようにしてRBのポジションに着く。
ファイターズファンが陣取ったレフト側アルプス席と外野席から万雷の拍手が送られる。立命との決戦で鮮やかな独走TDを挙げただけでなく、今季の攻撃陣を終始リードしてきた彼をどうしても甲子園のグラウンドに立たせたいというコーチとチームメートの思いを汲んだベンチの計らいだった。
試合後、グラウンドに降り、喜びで顔をくしゃくしゃにしているQB奥野やRB中村らの右腕にそれぞれマジックで「34」と書き込まれているのを見、それが山口自身の手で書き込まれたと聞いたとき、僕は思わず「よっしゃー。これがファイターズや」とコブシを握った。
近くの大村コーチに聞くと「早稲田さんに失礼かとも思ったんですけど、どうしても最後の場面ではけがで苦労したメンバーを出したかった。山口はもちろん、最後にけがをした西野にも思い切りパスを投げさせられたし、この1年以上、ずっとけがで苦しみながらパートを引っ張ってきた富永も走らせることができた。4年生最後の甲子園。努力してきたヤツが思い残すことのないようにしてやりたかった」という答えが返ってきた。
まるで浪花節の世界である。けれども、ファイターズにとっては、こうした浪花節のよう気配りは珍しいことではない。2013年、日大と戦った甲子園ボウルでは直前に大けがをした池田雄紀君を副将の鳥内将希君や主将の池永健人君らが抱きかかえるようにしてサイドラインに並ばせたし、翌年はこれまた甲子園ボウル直前にけがをしたWRの横山公則君を周囲の4年生が包み込むようにして入場門を入っていった。
共同通信の宍戸博昭さん(日大OB)が最近の自身のコラムにこんなことを書いておられる。「全盛期の日大は、篠竹監督の個人商店、ファイターズは組織で勝負する総合商社」「ゲームプラン、プレーのデザイン、コールを含めて、よくコーチングされた関学の選手は相手の弱点を見逃さないしたたかさと高い遂行力を備えていた」……。
少々褒めすぎのような気もするが、選手に高い精神性を求め、魂の根幹に触れる祈りと、人間の感情に訴え、熱き血を奮い立たせ、涙を共有する浪花節が共存し、融合するファイターズのたたずまいに接していると、なるほど、これが総合商社と呼ばれる理由かも知れないという気がしてきた。
| «前へ | 次へ» |